AIが当たり前のように浸透する時代で、勝つためのブランディング戦略をお伝えします。
それが、「コンテンツブランディング」です。
コンテンツマーケティングではなく、コンテンツブランディングなのです。
AIO(AI Optimization)、LLMO(Large Language Model Optimization)対策の手法を交えながら、実践的に解説していきます。
ブランディングとマーケティングの違い
そもそも、ブランディングとマーケティングの違いをうまく飲み込めている方も少ないかもしれませんので、「こういう理解をするとよい」ということをお伝えします。
ブランディングの特徴

ブランディングとは、企業が「みんなにこう思って欲しい」という願望の実現することです。言わずともみんなとの共通認識ができることです。
ブランディングそのものはゴールではなく、その他のすべての活動を「〜〜〜しやすくする」ための土台になります。説得のコストを省くことができるのです。
すでに経過した事象によって形成されるものがブランディングです。実施したというのは、行ってきた実績や活動、どの場所で何を言ったのかの記録などです。過去もしくは現在のものごとを見聞きして、「この会社って◯◯だよね」というブランドが形成されます。ブランドの形成は、過去や現在にベクトルが向くのです。
サービスを売るにしても、ブランディングができていると売りやすくなります。
「この企業の新商品なのであれば、きっと高品質なのだろう」というイメージがあれば、わざわざ「うちのサービスは高品質なのです」ということを言わずとも認識してくれます。
ブランディングがうまくいっていない場合は逆です。「うちは挑戦的で革新的な企業なのです」と言ったとしても、「この会社は保守的でレガシーな会社だ」と思われている場合、わざわざ挑戦的で革新的な会社である理由を説明して説得させなければなりません。この説明コストの一手間があらゆる企業活動に影響します。
なので、ブランディングに投資をすることは、すべての企業活動を「〜〜〜しやすくする」状態にすることができるのです。
マーケティングの特徴

マーケティングとは、企業が「みんなにこう行動してほしい」という願望を実現することです。
「買ってほしい」「CTAボタンをクリックしてほしい」「口コミを広げてほしい」というアクションを促します。マーケティングそのものがゴールになり、「売上の向上」「問い合わせ数の増加」「CVRの向上」など、実質的な利益を生み出します。
マーケティングは未来への期待です。「これを購入したら良いことが起きそうだから購入する」「これをやったら得をしそうだからやる」というように、過去ではなく未来にベクトルが向きます。
面白いのは、ブランディングがうまくいっていないとしても、マーケティングがうまくいくこともありますし、ブランディングがうまくいっているとしても、マーケティングがうまくいかないこともあるということです。
「うちの商品は高品質で素晴らしいと思ってほしい」という思惑があり、ユーザーも「この企業の商品は高品質で素晴らしい」と思っていたとします。しかし、だからと言って「じゃあ、購入しよう」という話はまた別です。
購入をする動機はそのユーザーの境遇やタイミングによります。
たまたまお金がないタイミングだったとして、しかし会社の都合ですぐに購入しなければならないとします。そいうすると、高品質な商品を素晴らしいと思っていても、予算都合と購入速度のスムーズさから考えた場合、「別の商品を購入しよう」となるのです。
マーケティングは、最適なタイミングで、最適な効果を生み出すゴールのために行うものなのです。なので、ブランディングがうまくいっているとマーケティングしやすくなりますが、必ずしもマーケティングがうまくいくとは限らないのです。
ブランディングはマーケティングのテクニックを超越できるときがある
| 項目 | ブランディング | マーケティング |
|---|---|---|
| 目的 | 「こう思ってほしい」という認識の形成 | 「こう行動してほしい」という行動の促進 |
| 時間軸 | 過去・現在の実績や活動によって形成 | 未来への期待に基づく |
| 役割 | あらゆる企業活動を「しやすくする」ための土台。説得コストの削減 | 「売上向上」など、それ自体がゴール。CVRの向上 |
| 効果の現れ方 | イメージが定着していれば、少ない労力でも拡散・好意的反応を得やすい | 優秀な人材・テクニック・予算で 短期成果を伸ばしやすい |
| 相互関係 | ブランディング弱でも、マーケ施策で短期成果が出ることも | ブランディング強でも、購入動機が合わず成果が出ないことも |
| 例 | 「この企業の新商品なら高品質だろう」と事前に思われる | 高品質だと思っていても、タイミングや予算で他社商品を選ぶこともある |
| 投資メリット | 中長期的に持続的な優位性を築く | 目標数値を達成するための短中期の解決策になる |
優秀なマーケターがいれば、商品の価値を巧みに伝えて、テクニカルなWeb広告運用を行い、企業は売上を伸ばすことができます。もしくは莫大な予算を投下して資金力で市場のシェアを取ることもできます。
ブランディングができている場合、そのような優秀なマーケター、テクニカルな技術、大きな予算がない場合でも、少ない労力で勝てたりします。
特に予算を投下しなくても、少しプレスリリースを出しただけで、「あの企業が新商品を出しただと!?きっと素晴らしいものに違いない!」と、たくさんのメディアが取り上げてさまざまな媒体で掲載されたりして、勝手に集客ができたりします。
優秀なマーケターが知恵と経験を振り絞って、テクニカルな運用を昼夜頑張ってやっと出した成果と同じような成果が、少しの労力で実現することもあります。
例えば、ひとつの雑誌広告をするとしたら、マーケティングのためにお金を支払って広告を掲載することが一般的です。しかし特定の分野でのブランディングがうまくいっている場合、雑誌側から「お金はいらないので、御社のことを載せてよいですか?」となる場合があります。
この事象は、雑誌のコンセプトと企業のブランディングがマッチしていて、このコンセプトならこの企業を呼ばなければならないというようなブランドが確立している場合に発生することがあります。
【本題】コンテンツブランディングの手法

では、そのようなブランディングをどのように実現するかの本題に入ります。ブランディングの話になると、よくAppleやスターバックスの話になることが多いと思います。ただ、彼らのような莫大な予算と試行錯誤して積み上げてきた戦略と施策の話と同じような動きをすることは多くの企業にとってはなかなか難しいものですし、もう土台となる時代が違います。
いまは、あきらかにAI時代です。AI時代に突入したからこそのブランディング戦略として、コンテンツブランディングを提唱し、どの企業でも取り組めるかたちでお伝えします。
どの企業でも取り組めるといっているのは、コンテンツブランディングの鍵となるものは、「事例」「経験」「社員」「顧客」という、どの企業も既に持っているものだからです。
「事例と言っても、人様に言えるような華々しい成功なんてないよ」
という方もいるかもしれませんが、そういうことではないのです。事例というのは、何も華々しい成功事例にとどまりません。小さなチャレンジ、当たり前のようにこなしたプロジェクト、失敗した経験など、普通に企業活動をしていれば、どのような会社でも持っている過去の出来事のことを指しています。
「そんなことを発信してブランディングにどうつながるの?」
と思われるかもしれませんが、AI時代では、そのような些細なことでさえも企業の生の一次情報としてコンテンツ化することができるのです。そして、その生の一次情報のコンテンツの積み上げこそが、「この企業ってこうだよね」という企業側と社会との共通認識を生み出すことができるのです。そして、AIによる情報検索体験の変化によって、コンテンツの積み上げが効いてくるのです。
コンテンツブランディングが効く理由
コンテンツブランディングが効く理由としては、AI時代の検索体験の変化による影響が多くあります。これまでSEOは重要なコンテンツ戦略でしたが、世の中の検索体験はAIの比重が増えてきていることもあり、AIO/LLMOの重要性が増しています。
AIO/LLMOは、ユーザーがAIに「◯◯について教えて」と言ったようなプロンプトを入力して情報を得ようとする場合などで、AI検索による要約や回答に引用してもらう手法です。つまり、これまでの『検索キーワードで上位表示させる(SEO)』という考え方から、『AIに良い回答材料として引用してもらう』という考え方にシフトしていく、ということです
GoogleやYahooなどの検索エンジンでの検索から、AIに質問して教えてもらうというAI検索の割合がどんどん増えていっていることを考えると、このAIO/LLMOはとても重要ということです。
AIがロジカルで網羅的で専門的な記事を量産してくれる
SEO対策記事コンテンツやAIO/LLMO対策記事コンテンツをつくる際に、もう既に多くの企業が「AIに記事を書かせる」ということをしています。
AIで作成した記事は、検索アルゴリズムに対して高品質な記事をつくることができます。ロジカルで、網羅的で、専門的と言った具合です。もはやほぼすべての人間よりも頭の良い知能をもつAIが書く記事ですので、それは優秀なわけです。
しかし、多くの企業がそれをしているが故に、検索でヒットする記事コンテンツが、同じような表面的な対策されつくした文章になることが起きています。みなさんも、調べたいことを検索した時に、上位表示された記事を読んで「あ、これはもっともらしいこと書いてあるが、たしかに否定はできないけど、表面上をなぞったつまらない記事だな」となる経験をした方もいるのではないでしょうか。
ようは頭の良い人が「こう書けばみんな納得するだろう」と書いた”温度のないロジカルで正当な文章”が記事としてアウトプットされているということです。
AIO/LLMOでは生の一次情報が重要になってくる
この記事を執筆している段階では、まだそのような量産型記事もAIは拾ってきていますが、この流れは変わってくるとコーレでは考えています。どのように変わるかというと、「検索ユーザーの境遇にマッチする温度のある記事」をAIは推薦するようになってくるということです。
AIは、ユーザーとの入出力のやりとりのコミュニケーションを通じて、どのような人物なのか、どのような背景を持っているのか、どのような境遇なのかを理解していきます。その境遇などを「コンテキスト」とすることで、ユーザーに対して検索結果をうまく選んだり、要約やおすすめしたりしてくれます。
この流れから考えると、「このユーザーはこういう人で、このような情報を知りたがっている。ということは、このロジカルで正当な記事コンテンツと、この生の一次情報を提供するとよさそう」という、「温度は低くて共感はできないけど正しい情報」と「正しいかよりも共感できる温度が高い情報」をうまく使い分けて提示するようになってきます。そして量産型記事の場合は、競合他社も同じような記事をつくることができるので、埋もれていってしまうことになります。
しかし、生の一次情報は別です。そのコンテンツを発信している企業にしかない唯一の情報になります。「◯◯という企業の、◯◯という人が、◯◯のタイミングで、◯◯をした結果、◯◯になり、そこから◯◯という考察を導き出した。そのときの様子がこちらの写真や動画である」というコンテンツは、世界中でそこにしか存在しない唯一のものになります。
そのような世界で唯一のコンテンツに登場する企業や人物の境遇が、検索ユーザーのコンテキストとマッチする場合、そのコンテンツは検索ユーザーによって超ドンピシャな情報になるのです。
AIは、常にユーザーにとって最善の動きをしてくれます。その超ドンピシャな情報は、これまでのSEOだけだと、検索ユーザーの検索能力によってたどり着くかつかないかという要因が大きくありました。
しかし、AIO/LLMOでは、検索ユーザーの検索力に左右されにくく、高知能なAIによってインターネットから高速に大量に情報を拾いにいき、超ドンピシャな情報をユーザーに当ててくれるのです。
鍵はコンテキストマッチ

検索ユーザーの背景(業界経験、企業規模、現在の課題)とコンテンツの背景(誰が、どんな状況で作成したか)がどれだけ一致するかというコンテキストマッチは重要です。
たとえば、従業員5000人の大企業の人事部長が転職情報を探している場合、同じく大企業の人事部長が書いた「リアルな組織改革の失敗談」というコンテンツにたどり着くことは、スタートアップの小規模チームの話より、はるかに没入感が高く、役立つと感じられるでしょう。このマッチング度合いが高いほど、ユーザーは「これこそ自分のための情報だ!」と共感することになります。
コンテキストマッチを実現するためにはコンテンツ量を多様に増やす
だからこそ、コンテンツを作成する際は、可能な限りユーザーの多様なコンテキストにマッチするよう工夫したいところです。しかし、これは一見当たり前のように聞こえますが、実は意外と難しい課題を抱えています。なぜなら、ユーザーの背景は無限に多様で、事前にすべてを予測して「ぴったりな」コンテンツを1つや2つ作るだけでは、カバーしきれないからです。
たとえば、特定の業界のベテラン向けに作った記事が、初心者ユーザーには「専門的すぎてついていけない」と感じられてしまうリスクがあります。結果として、せっかくの一次情報が埋もれてしまいます。
そこで鍵となるのが、「コンテンツの量を多様に増やす」ことです。単に数を増やすのではなく、多様な角度から生の一次情報を積み重ねることで、さまざまなコンテキストをカバーし、「超ドンピシャ」なコンテキストマッチを生み出す基盤を作り上げるのです。
多様なパターン例
事例はさまざまなパターンを生み出しやすいです。
華々しい成功だけでなく、日常の小さなチャレンジや失敗談を複数パターンでコンテンツにすることができます。写真や動画を添えて「その時のリアル」を加えると、よりユーザーの境遇に響きやすくなります。
社員インタビューは特におすすめで、バリエーションとして豊富に用意することができます。
異なる役職・経験レベルの社員にインタビューを行って記事化します。社員自体に記事を書かせようとすると、普段の忙しい中での追加作業になるので、それこそAIで表面的な記事をアウトプットされてしまいがちです。
なので、インタビュー形式でライブ的に情報を引き出すことによって、生の一次情報としてコンテンツ素材を収集することができます。インタビュー形式であれば、用意する質問の内容を変えたり、インタビューによって引き出した回答を深ぼる質問をしたりすることで、何度行っても新しい素材を生み出し続けることができます。
テーマをレベル別に細分化することもおすすめです。
同じテーマだとしても、「初心者向け」「中級者向け」「予算重視の場合」など、シナリオごとに分けてコンテンツを作成すると、ひとつのテーマから多様なアウトプットを生み出すことができますし、AIがユーザーのコンテキストを読み取りやすくなり、適切なものを推薦してくれやすくなります。
このようにコンテンツを大量に(ただし質を保ちつつ)積み上げることで、AI検索の時代では「この企業は私の状況をわかってくれている」との共通認識が生まれます。最初は手間がかかるかもしれませんが、積み重ねたコンテンツが雪だるま式にブランドを強化してくれます。
コンテンツの積み上げがブランドをつくる
コンテンツの積み上げが、結果として企業のブランドを形成していきます。その理由は、コンテンツが単発の情報提供ではなく、連続的な流れとして積み上がることで、企業の「ストーリー」になるからです。企業のストーリーがさまざまな場面で社会に発信されていき、社会との共通認識を徐々に築き上げていきます。AI時代では、この積み上げが雪だるま式に効力を発揮し、ブランドをオーガニックに定着させる力を生み出します。
最初はバラバラに散在したカケラのように見えるものですが、量が増えるにつれて、それらが繋がり、企業の全体像を描き出すことになります。
小さなプロジェクトの成功談、失敗からの学び、日常のチャレンジを次々とコンテンツとして発信していくと、1つだけでは「たまたまの出来事」だとしても、10個、20個、30個とコンテンツが増えていくと、「この企業は常に挑戦的で、柔軟性が高い」というイメージが形成されてきます。AI検索でユーザーが「革新的な企業の失敗例」を探した時、複数のコンテンツがヒットすれば、ブランドとしてのイメージが強化されるのです。
ただし、注意点もあります。素材をそのまま発信するだけでは、ユーザーに「理解しにくい」情報としてスルーされてしまうリスクがあります。情報にはお化粧が必要なのです。失敗事例をただ事実列挙しても、読み手は「だから何?」と感じるだけになってしまいます。そこで必要なのが、素材をクリエイティブで磨き、企業の思惑に沿った魅力を付加するブランドコンテンツに昇華させることです。
コンテンツ素材+クリエイティブの磨き→ブランドコンテンツ
素材を「磨く」ためには、「文章表現」と「視覚要素の付加」を行います。どちらも企業のブランドトーンに沿っって行います。
ブランドトーン
ブランドトーンというのは、ブランドの性格のようなものです。企業が何らかのコミュニケーションを取る際のスタイルを指します。
文章であれば、「ですます調」なのか、「である調」なのか、企業が普段発信する文章のスタイルがあるはずです。「フォーマルなのか、カジュアルなのか」「ユーモアを交えるか、真剣か」など、必ず特徴があるはずです。
他にも画像を使うことが多いのか、フォントは何を使うのか、文字の大きさはどれくらいなのか、文章量は短いのか長いのか、いろいろと個性が出てくるものです。
もしブランドトーンが決まっていない場合は、コンテンツブランディングをすることを機にして、ブランドトーンを策定しましょう。
文章表現
文章表現を磨くときには、主にストーリーテリングを行います。事実の羅列ではなく、素材を「起承転結」の物語形式に整理したりします。失敗事例を「問題発生 → 試行錯誤 → 解決 → 学び」の流れで語り、「その時の感情」を伝えると、これでコンテンツに触れているユーザーは「自分ごと」として没入します。
ロジカルな事実だけでなく、「当時の悔しさ」や「チームの喜び」などの感情要素を加えることで、「温度感」を意識的に乗せることができます。
視覚表現
視覚要素は、単なる「飾り」ではなく、情報の理解を深め、記憶に残るように設計するのがポイントです。AI時代では、検索結果でサムネイルやプレビューがパッと見の差別化要因となります。
コンテンツの内容としても、複雑な事例を視覚的に簡略化するとよいです。プロジェクトのタイムラインをチャートで表現したり、失敗原因をピクトグラムで分解したり、ツールとしてAIスライド機能や図解生成機能を使えば、誰でも簡単に作成可能です。そして、そこからさらに独自のブランドトーンを反映した色の調整や特徴の加工をします。こうすると、読み手は一目で全体像を把握でき、「この企業はわかりやすい」と好印象を抱きます。
さらに、生の一次情報を「リアル」に伝えるためにも、社員の現場写真や短い動画を加えられれば最高です。ポイントは、ただ貼り付けるのではなく、キャプションで文脈を説明することです。「この時のチームの熱気を感じてください」みたいな感じです。テキストだけでは伝わらない「雰囲気」や「人間味」が加わり、さらにユーザーの感情移入を促進できます。
ブランドコンテンツ
コンテンツ素材を集めて、ブランドトーンに沿ってクリエイティブを磨き、ブランドコンテンツが完成します。この一連の流れを作ることができれば、あとはひたすら繰り返してブランドコンテンツを作り続けていくと、コンテンツブランディングが実現していきます。
コンテンツブランティングの具体的な進め方

ここからは、コンテンツブランディングをいざ進めていく場合のHowの部分をお伝えします。汎用的な進め方としてお伝えするため、いざ実践する際には社内の都合にあわせて詳細に詰めながら進めていくことになります。自社だけでは難しそうな場合は、コーレにご相談ください。
ブランディング意図を決める
どのようなブランディングをするのか、企業の「理想の姿」をまとめます。「革新的で信頼できるAIパートナーとして認識されたい」や「親しみやすく、日常を豊かにするブランドになりたい」といった具合です。ここはミッション・ビジョン・バリューなど、企業のパーパスや理念に沿ったものがあると思います。
もしそれらに沿った思想がすでに社内に浸透していて、会社が一体となっているのならよいですが、そうではないことが多いのが実情だったりします。
現実的にはそのようになっていることが多く、部門ごとにバラバラだったりします。本質的には、「では、これを機にあらためてガッツリ策定しましょう」としたいところですが、担当者の現実としては「ミッション・ビジョン・バリューを変えるとなると、それはまた一大プロジェクトになるから、そこまでおおごとにするのは大変なんだよなぁ」という声が聞こえてきます。
なので、そこまで大きな動きはできないけど、コンテンツブランディングの波に乗りたいという場合には、今回のコンテンツブランディング用にブランディング意図を定めることを推奨します。
冒頭で説明したように、ブランディングとは“企業が「みんなにこう思って欲しい」という願望の実現すること”です。コンテンツを通じて、社内、社外、社会からどのようなイメージを持ってもらいたいのかを言語化しましょう。
コンテンツ発信方法を決める
ブランディング意図が決まったら、何の媒体でコンテンツ発信をしていくかを決めます。自社のオウンドメディアサイトをつくるのか、ホームページについているCMS機能でやるのか、note、Qiita、Zennなどを使うのか、これは決め打ちになります。
ブランドトーンの策定
次にブランドトーンを策定します。すでにブランドトーンがある場合はこのステップは省略してください。もしまだブランドトーンがない場合、しっかりと作ろうとすると結構な時間がかかります。もしできるだけ早く始めたい場合は、最低限として以下のブランドトーン策定表に沿って決めるとよいです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 言葉遣い | ですます調 |
| 感情のニュアンス | 喜怒哀楽多め |
| 文構造のルール | 長文形式で細かく説明する |
| 禁止/推奨ワード | 禁止:意識する→推奨:集中する |
| 色 | 白と黒と赤 |
| フォント | Noto Sans |
| ビジュアルスタイル | 余白広め。イラスト多め。アイコンは赤色。 |
コンテンツ素材集め
ブランドトーンが決まったら、つぎはコンテンツ素材集めです。このステップがもっとも大変になります。コンテンツ素材をゼロから生み出そうとすることは、なかなかハードルが高いです。コンテンツブランディングのコツとして、労力を省エネで持続的に行うことが重要です。
コンテンツをつくっていこうとすると、どうしても最初の方はクオリティが高いものをつくりたくなります。しかし、1つのコンテンツをリリースするために膨大な労力をかけていると、どこかの忙しなったタイミングで後回しになり、納期が後ろになり、そのうち更新されなくなっていきます。他の通常業務で忙しくなったとしても、省エネで持続的にコンテンツを生み出し続けられる体制と運用が重要です。
省エネでコンテンツ素材を生み出していくには、すでに社内にあるアセットを使うべきです。その最もおすすめなのが「社員」です。そして社員インタビューをすることで、コンテンツを生み出していきます。
社員インタビュー方法
インタビュー対象者をリストアップします。インタビュー対象者の時間を30~60分調整します。省エネで実現するために、オンラインでのインタビューにしましょう。
インタビューでは、必ず録画機能を使います。オンラインMTGツールについていればよいですが、そうではない場合は他の録画ツールを活用しましょう。録画をすることは必須です。
あらかじめ定めてあるブランディング意図に沿って、どのような回答を引き出すかをイメージしましょう。世の中に出ているすべてのインタビュー記事は、ほぼすべて取材元の思惑が介入しています。まっさらにフラットな状態でインタビューをすることはなく、最終的に発信されるコンテンツ媒体にあわせた「狙い」があるものなのです。
あらかじめ質問リストをつくり、インタビュー対象者に質問していきます。
- 最近取り組んだプロジェクトで、最も印象に残った出来事は何ですか?
- チーム内で協力して達成した成功事例を具体的に教えてください。
- 日々の業務で、会社の価値観がどう体現されていると思いますか?
- AIツールなどの新しい技術を業務に取り入れた経験はありますか?
- 顧客との関わりで、心に残るエピソードはありますか?
- 仕事のやりがいを感じる瞬間はどんな時ですか?
しかし、質問リスト通りに進んでいくことはまずありませんし、それだけでは大した回答は引き出せないことが多いです。重要なのは、質問の回答を深ぼる質問をすることになります。この「深掘り質問」こそ、インタビュー対象者が秘めているコンテンツ素材の原石です。
深掘り質問をするためには、「もともとの質問の意図」「相手の回答の理解」「回答をさらに深ぼる観点」が必要になるので、高度なコミュニケーション能力が必要になります。
そこでおすすめなのが、AIによって深掘り質問をリアルタイムで生成することです。相手の回答内容をコピーして、AIに「この回答が来ました。さらに深ぼるための質問をつくってください」とプロンプト入力すれば、頭の良いAIが深掘り質問をつくってくれます。インタビューする方は、それを対象者に質問すればよいのです。
●深掘り質問プロンプト
いままさに、採用活動に活用するため、株式会社◯◯の社員インタビューをしています。
インタビュー対象から以下の発言がありました。
発言内容をさらに深掘り、インタビュー対象からよりユニークで価値のある発言を引き出すための深掘り質問を1つだけ出力してください。
●発言内容
ここにコピペそうやって質問を重ねていき、30~60分もあればかなりのコンテンツ素材を集めることができます。最後にオンラインMTGでインタビュー風景としてスクリーンショットを撮影しておきましょう。スクリーンショット1枚あれば、あとはAIの画像生成機能や編集機能で、さまざまなクリエイティブ素材として使うことができます。
コンテンツ素材の加工
インタビューが終わったら録画データを保存します。録画データをもとに、コンテンツ発信をするための型として整形しましょう。ここはプロンプトエンジニアリングの領域になります。インタビュー内容の原型を崩さず、でも魅力的な内容になるよう、うまく文章を整形したり、ストーリーを付与したりします。
コンテンツを発信する媒体のブランドトーンにも合わせてプロンプトを磨いていきましょう。プロンプトエンジニアリングでは、出力内容のコントロールをする場合は高度なテクニックが必要になります。もし慣れていない場合は、専門家に手伝ってもらいましょう。
出力された文章を、最終的に手作業で調整して文章のクオリティを高めていってもよいのですが、省エネで行うことが重要です。ここにリソースをかけて、コンテンツ発信のハードルが上がってしまって、更新が止まってしまうことが一番避けたいポイントです。
そのあたりはリソースの塩梅をみて調整しましょう。コンテンツブランディングでは、とにかく「生の一次情報を発信し続けること」が本質的に重要なので、コンテンツ1本のクオリティをあげるよりも、「一次情報のコンテンツである」ということがはるかに重要です。
画像・動画の追加
文章が完成したら、画像を追加していきます。インタビュー形式のコンテンツであれば、インタビュー対象の写真画像は鉄板です。1枚の写真があれば、それをデータとして画像生成AIに読み込ませて、複数のポーズやスタイルの写真画像を生成することもできます。

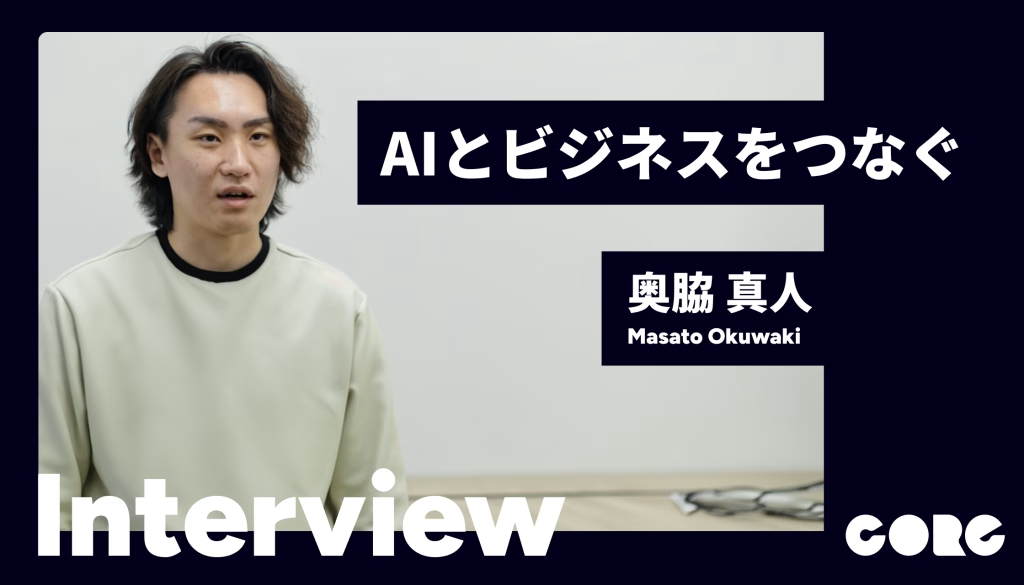
コンテンツのサムネイル画像や、記事内に挿入する画像をつくっていきましょう。ここもリソースとの兼ね合いになります。サムネイル画像などのメイン画像1枚があればひとまず問題ありません。
コンテンツの投稿
文章とクリエイティブが揃ったら、あとは媒体にコンテンツを投稿します。これで1つのコンテンツがリリースできました。
おわりに
ここまで、コンテンツブランディングの全体像と具体的な進め方をお伝えしてきました。ブランディング意図の策定から始まり、ブランドトーンの設定、社員インタビューによる素材集め、クリエイティブの磨き、そして投稿まで。
これらを繰り返すことで、企業の生の一次情報が積み重なり、「この企業は、こういうブランドなのか」との共通認識が生まれます。AI検索の時代では、この積み上げが大きな成果を生む強力な武器になるのです。
最初は「本当にこれでブランドが築けるのか?」と不安になるかもしれませんが、大切なのは省エネで持続的に発信し続けることです。
1本のコンテンツから始め、フィードバックを活かしながら量を増やしていきましょう。AIを上手に活用すれば、実現可能です。あなたの企業が、AI浸透の波に乗り、独自のブランディングが実現できるようになるはずです。
お問い合わせお待ちしています
コーレは、コンテンツブランディングの実行支援を行っています。
お気軽にご連絡ください:https://co-r-e.net/contact/

