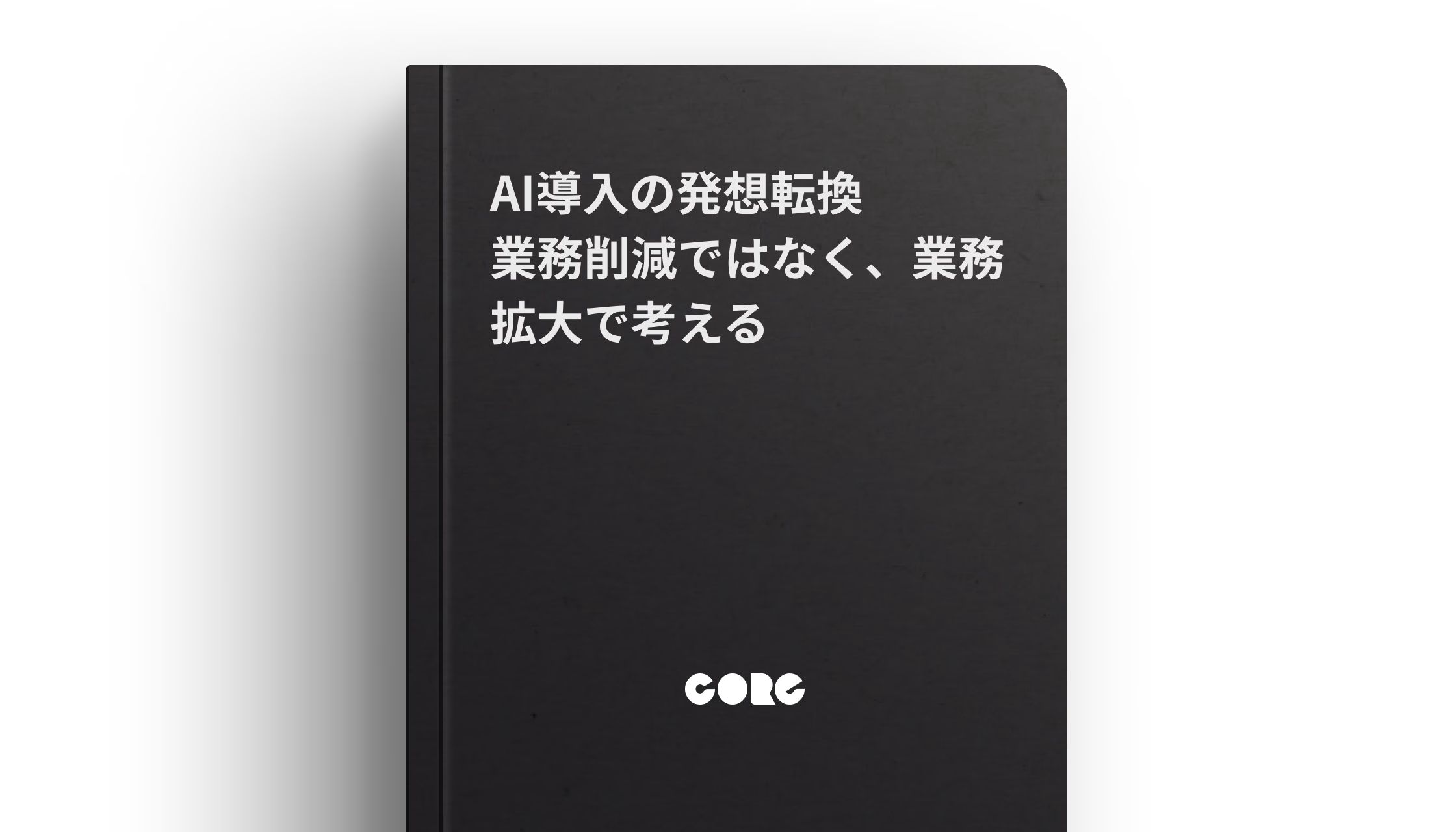AI導入プロジェクトの多くが陥る罠
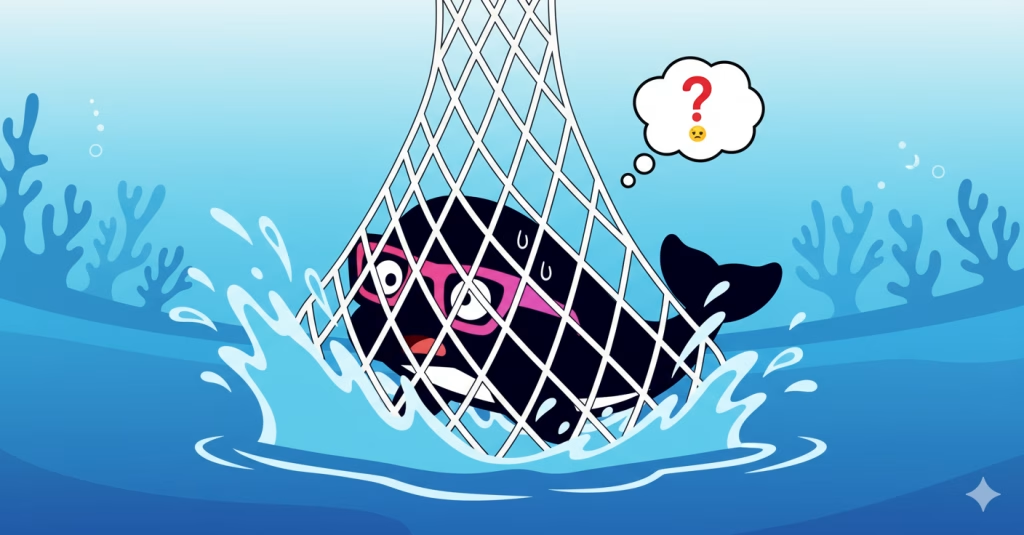
昨今、多くの企業でAI導入プロジェクトが立ち上がっています。しかし、その多くが思うような成果を上げられずに終わってしまうのが現実です。私たちも数多くの企業のAI導入を支援してきましたが、そこで見えてきたのは、多くの企業が「AI導入の入口」で躓いているという事実でした。
なぜAI導入プロジェクトはうまくいかないのか。その最大の原因は、「アイデア」にあります。
多くの企業では、AI導入プロジェクトチームが組成されると、まず現場へのヒアリングから始めます。「現場で大変なことは何ですか?」「AIを使って効率化したいことはありますか?」こうした問いかけは一見合理的に思えますが、実はこれこそが失敗の始まりなのです。
「業務削減」という発想が生む現実離れした要求
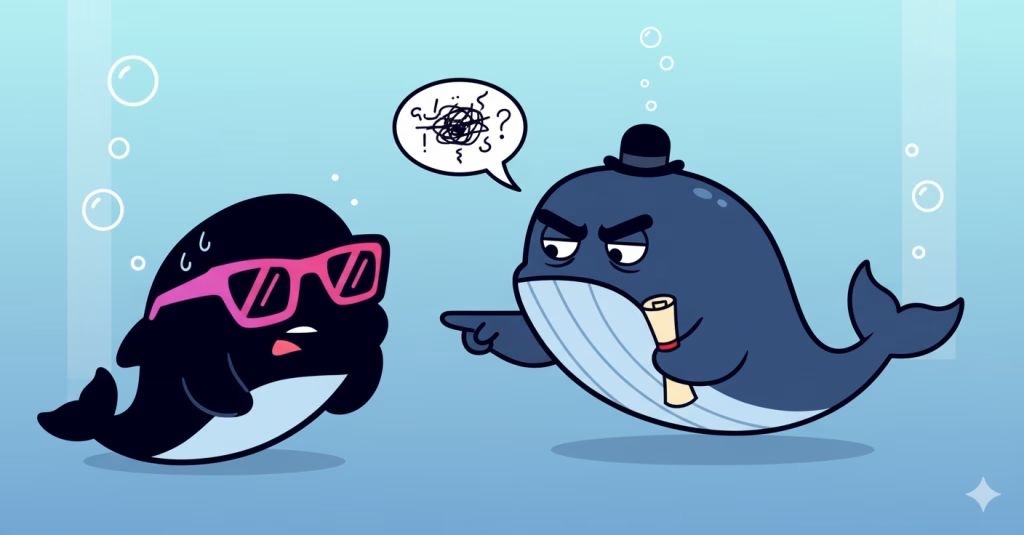
このような聞き方をすると、現場からは必ずと言っていいほど「それは無理だよ」というアイデアが返ってきます。なぜなら、多くの人は「AIで業務効率化をして、今人間がやっている仕事を楽にする」「時間を短くする」という発想でAI活用を考えてしまうからです。
この「業務削減」という発想が、実は大きな問題を引き起こします。人間が長年かけて習得してきた複雑な判断や、微妙なニュアンスを含むコミュニケーション、暗黙知が必要な業務など、現時点のAIでは完全に代替できない業務が山ほどあります。そうした業務を「AIで楽にしたい」と考えると、どうしても現実的ではない無茶な要求になってしまうのです。
結果として、「やっぱりAIは使えない」「導入しても効果が出ない」という結論に至り、プロジェクトは頓挫してしまいます。これは非常にもったいないことです。なぜなら、AIには確かに大きな可能性があるにもかかわらず、アイデアの段階で誤った方向に進んでしまっているからです。
発想の転換:業務量が2倍になったらどうするか

では、どうすればいいのか。私たちの提案は、発想を180度転換させます。
「AI導入で狙うべきは、業務削減ではない」
このことを、AI導入に関わるすべての人に理解していただきたいと思っています。具体的にどう発想を転換するかというと、こう考えてみてください。
「今の人数を変えないとして、業務量が2倍になった時にどうやって業務をさばくか。しかも品質を落とさず、むしろ品質を上げながら。」
この発想転換を行うと、不思議なことにAIをどのように活用しようかという現実的なアイデアが湧いてきやすくなります。
なぜこのアプローチが有効なのか。それは、「現在の業務を楽にする」という守りの発想ではなく、「業務を拡大させる」という攻めの発想に切り替わるからです。業務を削減するのではなく、業務を拡張する。人間がやるべきことはそのままに、AIに新たな役割を担わせる。この発想の違いが、実現可能で効果的なAI活用のアイデアを生み出すのです。
実践的なヒアリング手法

では、現場へのヒアリングをどう変えればいいのか。私たちが推奨するのは、次のような問いかけです。
「人数を増やすことはできないのですが、3ヶ月後に業務量が2倍になります。人を増やすことはできません。クオリティを落とすことも許されません。どうしますか?」
一見すると厳しい条件に思えるかもしれません。しかし、この問いかけには明確な意図があります。
まず、「人を増やせない」という制約を明示することで、人的リソースに頼った解決策を排除します。次に、「クオリティを落とせない」という条件により、単純な業務の省略や手抜きも選択肢から外します。そして最も重要なのが、「業務量が2倍」という具体的な数字です。
この制約条件の中で考えると、現場の人たちは自然と「今と同じやり方では絶対に無理だ」という認識に至ります。そこから、「何かを変えなければならない」「新しいツールや仕組みが必要だ」という思考が始まるのです。
こうして出てくるアイデアは、「AIで楽をしたい」という発想から生まれたものとは質が全く異なります。具体的で、実現可能で、そして本当に業務にインパクトを与えるAI活用の方法が見えてくるのです。
なぜ「業務拡大」の発想転換が有効なのか

この発想転換がなぜ効果的なのか、もう少し説明します。
第一に、AIの得意領域が見えやすくなるという点があります。業務削減を考えると、「人間の仕事をAIに置き換える」という発想になりがちですが、現状のAIは人間の完全な代替にはなりませんし、人間の業務の棚卸し工数が大変です。一方、業務拡大で考えると、「人間がやっている仕事の一部をAIがサポートする」「AIが新しい価値を追加する」という発想になります。これはAIの得意領域とマッチしています。
第二に、具体的なユースケースが見えやすいという利点もあります。「2倍の業務量」という具体的な数字があることで、「どの業務プロセスをどう変えれば2倍に対応できるか」という具体的な議論ができます。抽象的な「効率化」ではなく、具体的な「このプロセスをこう変える」という話になるのです。
第三に、投資対効果が明確になります。業務量が2倍になるという前提があれば、「そのために必要な投資はいくらか」「それによって得られる効果はいくらか」という議論が明確になります。売上を2倍にしながら、リソースコストを変えないとする。つまり投資対効果を明確な利益として算出することができます。単なる「効率化」では測りにくかった効果が、「2倍の業務量に対応できる」という形で可視化されるのです。
AI導入の本質は「能力の拡張」にある
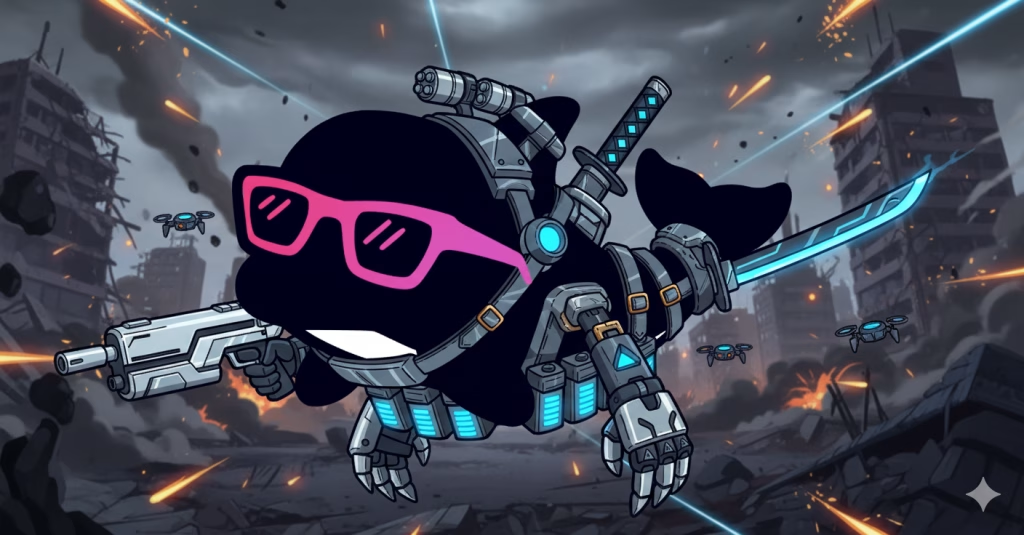
私たちがAI導入支援を通じて目指しているのは、AIを活用して組織の能力を拡張することです。業務プロセスの整理・可視化から始まり、最適なAIの提案、実装の要件整理まで、一貫してサポートできるのは、私たちが様々な新規事業開発に関わってきた中で培った「ビジネス解像度の高いAI開発」の知見があるからです。
AIは業務を削減するためのツールではありません。1人あたりの捌ける業務量を増やし、組織の能力を拡張し、より多くの価値を生み出すための「ブースト装置」なのです。
人を減らすためではなく、同じ人数でより大きな成果を出すために。 時間を削るためではなく、より質の高い仕事に時間を使うために。 楽をするためではなく、より難しい課題に挑戦するために。
こうした「攻めの姿勢」でAI導入を考えることが、本当の意味でAIを活用し、組織を成長させる第一歩となります。
まとめ

AI導入を成功させるためには、まず発想を変えることが必要です。
「業務削減」ではなく「業務拡大」。 「楽をする」ではなく「能力を拡張する」。 「今の仕事を減らす」ではなく「より多くの仕事を捌く」。
そして、現場へのヒアリングも変えましょう。「大変なことは何ですか?」ではなく、「業務量が2倍になったらどうしますか?」「いまの2倍のアウトプットをするならどうしますか?」と。
この問いかけの違いが、AI導入プロジェクトの成否を分けます。もし皆さんの組織でAI導入を検討されているなら、ぜひこの発想の転換を試してみてください。きっと、今まで見えていなかったAI活用の可能性が見えてくるはずです。
PC画面のすべてに寄り添うAI「IrukaDark(イルカダーク)」

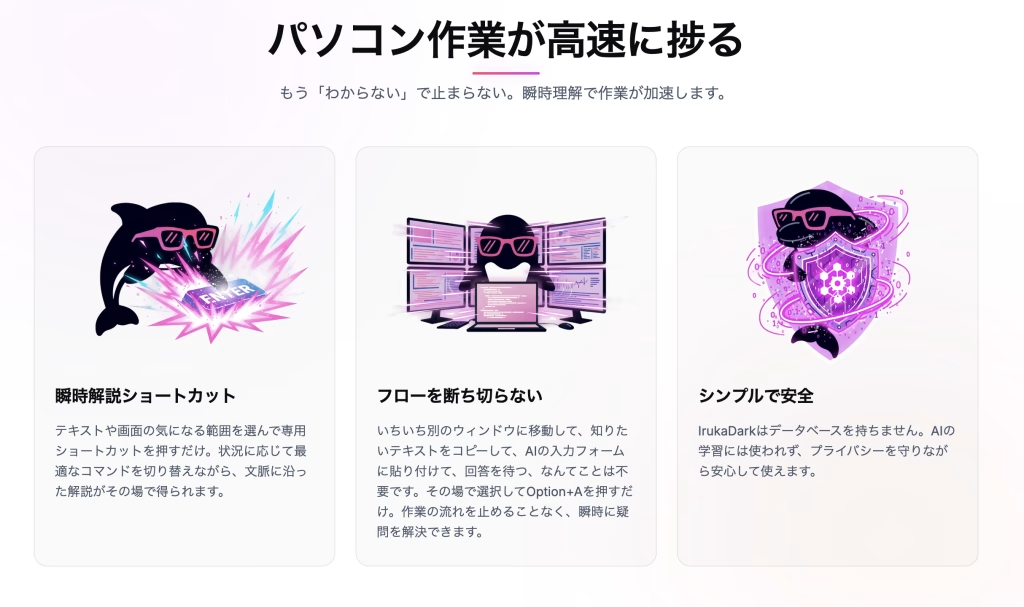
コーレでは、PC画面に常駐してなんでも超高速に教えてくれるAIを無料提供しています。https://youtube.com/watch?v=-6r4QpIRlUM%3Ffeature%3Doembed
こちらのサービスサイトから詳細をご覧ください。
無料で提供中:https://irukadark.com/ja