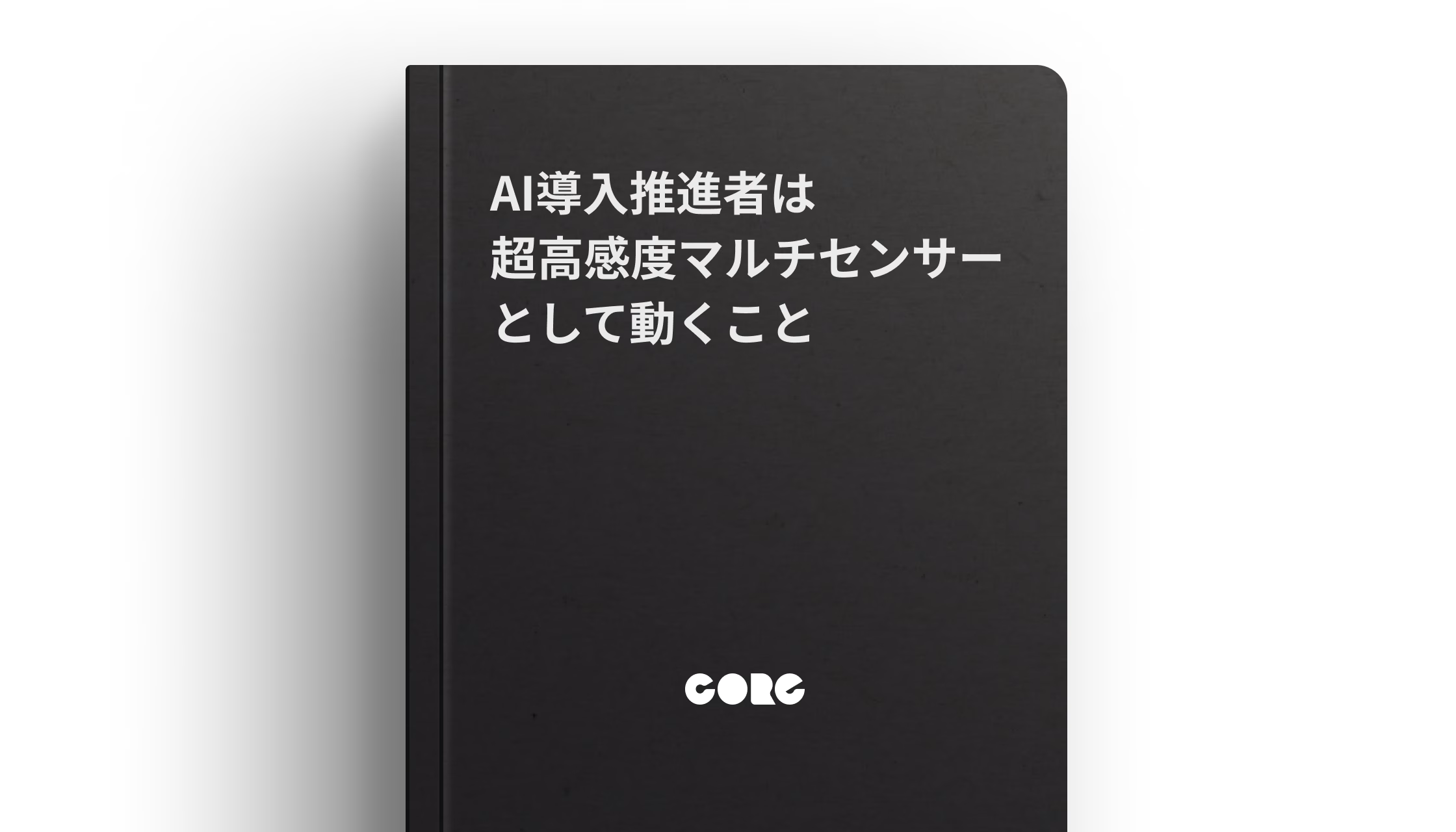組織のAI活用を進めていくためには、AI導入推進者が必要になってきます。ゴリっと力強くAI導入を進めていくにあたり、AI導入推進者は自らを超高感度マルチセンサーとして捉えることが必要です。この認識があると、社内のあらゆる会議は情報の宝庫に見え、社内飲み会や経営合宿などもデータ収集のとんでもないチャンスとして認識することができます。
人間を超高感度マルチセンサーとして捉える

人間は、極めて高性能なマルチセンサーと言えます。五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)をはじめとした多様なセンサーを備えています。さらに、感情、直感、コンテキスト理解といった抽象的な知覚も加わり、世の中の情報を多角的に大量にインプットすることができます。
たとえば、会議室の空気感を想像してみてください。AIはテキストや音声データを分析できますが、人間は「参加者の微妙な表情の変化」「声のトーンに込められたニュアンス」「部屋の緊張した雰囲気」を瞬時に検知します。これらは、数字化しにくい「質的データ」ですが、ビジネスでは極めて重要です。人間センサーは、こうした微細な情報を収集することができます。
【AIによる出力】プロンプト:センサーとして人間の規格を五感ごとに書いてください
視覚(Vision)
人間の視覚センサーは、波長約380-780nmの可視光を検知。
中心視野の解像度は約60アーク秒/ピクセル(約1メガピクセル相当)
周辺視野を含むと広角で動体検知に優れ、色識別は約1000万色。
リアルタイム処理で深度・動きを推定。
聴覚(Hearing)
周波数範囲は20Hz-20kHz(加齢で低下)。
音圧レベルは0-140dBまで検知可能。
方向定位精度は約1-2度、立体音像再現でエコーやノイズから情報抽出。会話レベルで感情やニュアンスをリアルタイム解析。
触覚(Touch)
皮膚表面の圧力(0.1g/mm²以上)、温度(0.1℃差)、振動(1-1000Hz)、痛み・かゆみを検知。解像度は指先で約0.5-1mm。
マルチポイント入力可能で、質感・硬度・形状を総合判断。
味覚(Taste)
基本味(甘・酸・酸・甘・塩・苦・旨)を舌の味蕾(約2000-8000個)で検知。
閾値は甘味0.001M、苦味0.000001M。
嗅覚と連携し、10万以上の風味を識別。
安全性評価に特化。
嗅覚(Smell)
約400種の受容体で、10,000以上の臭気分子を検知。
閾値はppbレベル(例: メルカプタン1/10^10)。
記憶・感情連動で微量ガスや環境変化をリアルタイム警戒。
方向性は低いが、持続性高。リアルタイムかつ統合的な情報処理

さらに重要なのは、人間はこれらのセンサーから得た情報を、リアルタイムで統合的に処理できることです。会議室に入った瞬間に感じる「なんか今日は雰囲気が違うな」という直感は、視覚、聴覚、嗅覚、温度感覚などが瞬時に統合された結果です。
このような統合的な感知能力は、現在のAIやIoTセンサーでもまだ実現できていません。人間は、毎秒膨大な量の環境データを取り込み、過去の経験と照らし合わせて、瞬時に状況を判断しているのです。
スーパーローカルを特定する
| データ化レベル | 説明 | 特徴 | 課題 |
|---|---|---|---|
| スーパーローカル | それぞれの社員の頭の中にだけ存在する情報(経験、勘、暗黙知) | 属人的で共有しにくい。人間のセンサー機能が最も活きる領域。 | データ化されていないため、AIがアクセス不可。業務のブラックボックス化を招く。 |
| ローカル | それぞれの社員のPCのローカルファイルに保存された情報(個人メモ、ドラフト)。 | 個人のデバイスに限定。共有は可能だが、手間がかかる。 | セキュリティリスクあり。データ紛失の恐れあり。 |
| プライベートクラウド | 会社内クラウド環境で管理されている情報(共有ドライブ、社内システム)。 | 組織内でアクセスが容易である。最新版を共有するなど複数名によるバージョン管理が可能。 | 社外からのアクセス制限により利便性に欠けることがある。データ量が増大すると検索性が低下する。 |
| パブリッククラウド | 社外にもオープンにしている情報(公開資料、Webサイト、プレスリリース)。 | 誰でもアクセス可能。社外のAIの外部学習にも活用されたりする。 | 機密情報を載せてはいけない。社外の目に触れるため、品質管理が必要。 |
多くの企業で「属人的になっている業務が問題視される」のは、スーパーローカルな情報の存在が原因です。スーパーローカルな情報とは、社員の頭の中にしかなく、共有されていない知識やスキルのことです。例えば、ベテラン営業マンの「顧客の好みを察知する勘」は、なかなか後継者に引き継げません。
業務において、どのようなスーパーローカルな情報があるのかは、業務を行っている本人すら気づいていないことも多くあります。AI導入推進者は、センサーとしての役割で業務を観察する必要があります。業務の観察方法は、「精密な現状把握」の手法で実現できます。
スーパーローカルを特定し、自らをセンサーとして業務の現状把握を特定したら、そこからついにAI導入を推進できる企画の段階になります。
喋らない会議も無駄ではない
これまで、「会議で発言しない人は、その会議にいる意味がない」ということが多くの場で言われてきました。しかし、AI導入推進者であれば話は別です。もし発言をしないとしても、その会議にセンサーとして設置することで、会議で交わされるさまざまな情報をインプットさせることができます。
「AIで要約した議事録でいいじゃん」
と思われるかもしれませんが、AI導入の観点ではそれだけだとデータ不足なのです。AI導入は、社内のさまざまなステークホルダーの関係性や、業務がリアルにはどのように行われているのかなどによって大きく変わるものです。議事録の文字情報だけではうまく進まないことも多く、会議などのライブ感のある場での情報のやり取りをキャッチアップすることが重要です。
AI導入推進者は、喋らないとしても、データ収集目的で会議に参加することがおすすめです。
お問い合わせお待ちしています
コーレでは、AI導入推進者に伴走する手厚いサポートをすることが可能です。社内のAI導入推進者を選抜してから、いざ何から手をつけようかと悩んでいたり、なかなかプロジェクトの推進が進まない場合などがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。:https://co-r-e.net/contact/