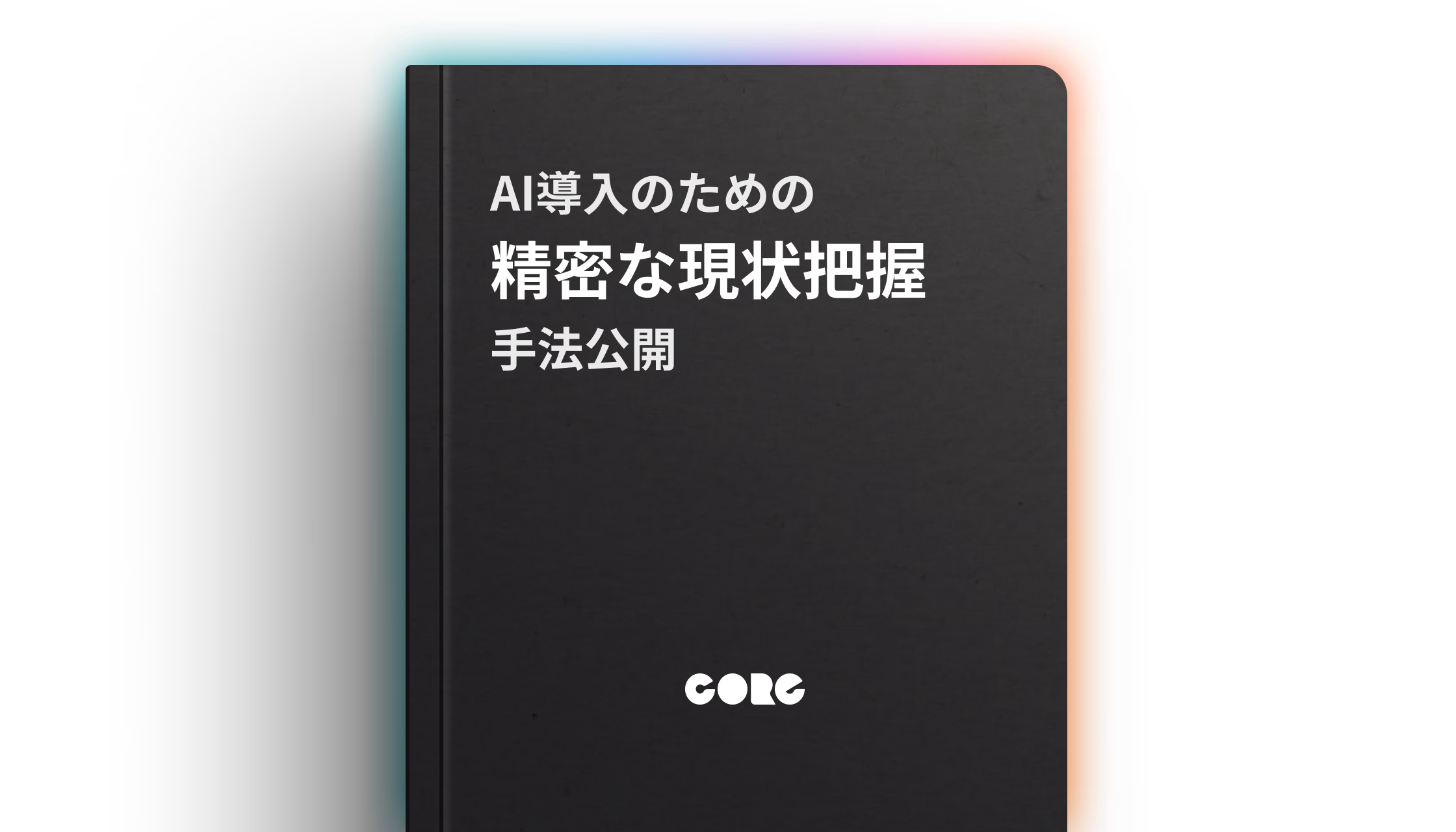コーレでは、精密な現状把握をすることからプロジェクトが進みます。
「動的な把握(人・組織のリアルな動き)」と「静的な把握(文書・データの客観的な事実)」を掛け合わせることで、初めてプロジェクトの全体像が立体的に見えてきます。片方だけでは、必ず重要なことを見落とします。
AI導入プロジェクトでは、スピード感が求められることが多いものです。その中でも、プロジェクトを着実に前進していくためにも、クライアントにも協力してもらいながら、精密な現状把握をしてからプロジェクトを進めていきます。
この記事では、その「精密な現状把握」をする方法をお伝えします。
動的な現状把握(人、組織、文化の“生きた情報”を捉える)
AI導入の成否は、技術的な要素以上に、それを使う「人」と、その人が属する「組織」に大きく左右されます。したがって、現状把握は、まず、文書やデータからは読み取れない、生きた情報を捉えることから始めます。
ミーティングへのオブザーバー参加

プロジェクトに関連する公式・非公式な会議に観察者として参加し、テキスト情報だけでは得られない組織の「生きた力学」や「暗黙のルール」、「コミュニケーションのスタイル」を肌で感じ取ること。これは、以降のすべてのアセスメントの精度を左右する、最も重要な初期活動です。クライアントから「うちの会議は大したこと話さないですよ」と言われる場合でも、その「話さない」という事実自体が重要な情報となります。
| 参加するミーティングを決める |
|---|
| プロジェクトの意思決定に関わる会議 |
| AI導入の対象となる業務の定例会議 |
| 部門間の連携会議 |
| マネージャー層が参加する会議 |
| 経営層が参加する会議 |
| 見るべきもの①発言の性質 |
|---|
| Fact vs Opinion 発言は、客観的な事実(Fact)に基づいているか、それとも個人的な意見や感想(Opinion)か。 |
| 定量的 vs 定性的 「売上が落ちている」といった定性的な表現か、「売上が前年同月比で15%低下している」といった定量的な表現か。 |
| 課題志向 vs 責任追及 議論は、未来の課題解決に向かっているか、過去の失敗の責任追及に向かっているか。 |
| 見るべきもの②発言者 |
|---|
| 誰が議論をリードしているか。 |
| 誰が最も多く、あるいは最も重要な発言をしているか。 |
| 逆に、本来発言すべき立場の人間が沈黙していないか。その沈黙は「同意」なのか「諦め」なのか「無関心」なのか。 |
| 見るべきもの③意思決定のプロセス |
|---|
| 決定メカニズム 最終的な意思決定は、特定の権威者によるトップダウンか、関係者の合意形成(コンセンサス)か、多数決か。 |
| 決定のスピード 課題に対して、その場で即座に結論が出るか、あるいは「持ち帰り検討」「一旦保留」といった形で先送りされがちか。 |
| 根回しの存在 会議の場で初めて議題が共有されるのか、それとも、すでに水面下での調整(根回し)が終わっているように見えるか。 |
| 見るべきもの④力学 |
|---|
| 誰が誰に注意を払っているか。誰の発言が引用され、誰の発言がスルーされるか。 |
| 対立や、協力的な雰囲気はあるか。 |
| 発言者が変わると、会議の緊張感や雰囲気がどう変化するか。 |
| 見るべきもの⑤使う言葉 |
|---|
| 専門用語や業界用語、三文字略語(アルファベットの略語)がどのくらい飛び交うか。 |
| 社内だけで通じるスラングや独特の言い回しはあるか。(これらは組織文化を色濃く反映します) |
キーパーソン・インタビュー

オブザーバー参加で特定した、プロジェクトの鍵を握る人物(キーパーソン)に対し、1対1のクローズドな環境で、「本音」「個人的な動機」「モヤモヤした懸念」を引き出すことをします。
| インタビュー対象者選定 |
|---|
| プロジェクトオーナー |
| AI導入対象部門の責任者、現場マネージャー |
| AI導入に協力的と思われる「推進派」 |
| AI導入に懐疑的・抵抗感を持つと思われる「慎重派」 |
| 情報システム部門、IT部門、DX推進部門の責任者、担当者 |
業務プロセスのウォークスルー

担当者と共に、実際の業務プロセスを最初から最後まで追体験します。ウォークスルーをすることで、マニュアルや手順書だけでは分からない、業務の「行間」にある暗黙知、非効率な作業、担当者のリアルな判断基準を可視化します。
| 準備 |
|---|
| 対象業務の手順書やマニュアルを事前に読み、「ここの判断基準は?」「この手入力は本当に必要か?」といった質問の仮説を立てておく。 |
| 実際の業務で使うシステムやツールを、その場で操作してもらえる環境(スクリーン共有など)を準備する。 |
| ウォークスルーのポイント |
|---|
| Show, Don’t Tell(語らせるな、見せさせろ) 「この場合はどうやりますか?」と聞いたときに口頭で返事をしてもらうのではなく、「この場合はどのような操作をするか見せていただけますか?すみませんが実際に見たいのです。」と依頼する。 |
| 判断基準のヒアリング 「この金額とこの金額で迷った場合、どのように最終判断をしていますか?」と、判断基準を具体化する。 |
| もし 「もし、このデータが間違っていた場合、どういう手順で修正しますか?」と、マニュアル外の例外処理を聞き出す。 |
| 感情調査 「正直なところ、この一連の作業の中で、一番『面倒くさい』と感じるのはどの部分ですか?」を聞いて感情的な反応をみる。 |
業務プロセスのシャドーイング(業務随行観察)
担当者の隣や、常時画面共有の状態で、特定の業務を行う様子を「介入せずに」長時間観察することです。ウォークスルーが「質問しながらの見学」であるのに対し、シャドーイングは「純粋な観察」であり、思考の時間や、ふとした瞬間の独り言、他の社員との短いやり取りなど、より自然な業務実態を捉えることを目的とします。
| シャドーイングのポイント |
|---|
| ひたすら静観する 途中で口を挟まずに、ひたすら観察して、最後に質問ポイントをまとめて聞く。 質問をするまでは、気になることがあっても耐えて空気のように存在感をなくす。 |
オペレーション・レコーディング(非同期型ウォークスルー)
リアルタイムでのウォークスルーやシャドーイングが困難な場合に、担当者に実際の業務操作を動画で撮影・共有してもらうことで、時間や場所の制約なく、現場のオペレーションを正確に把握します。
単に「動画を撮ってください」と依頼するのではなく、相手の負担と不安を解消するためのコミュニケーションが不可欠です。
| オペレーション・レコーディングのポイント |
|---|
| 心理的ハードルを下げる言葉を添える 「完璧な動画である必要は全くありません。途中で操作を間違えたり、言い間違えたりしても、編集せずそのままお送りください。むしろ、そういった『普段通りの姿』が最も貴重な情報です。」と伝えて障壁を下げます。 |
最小の高速コミュニケーション

こちらとのメインで連絡を取る方に、公式な報告の場以外で、日々の小さな気づきや変化、インフォーマルな情報を、リアルタイムかつ気軽に共有してもらうための専用チャネルを構築・運用することです。
| 最小の高速コミュニケーションのポイント |
|---|
| 「プロジェクトの生きた“脈拍”を知りたいので、日々の小さな変化を感じたら教えてください」と依頼する。 |
| 「皆さんにとっては“情報のカケラ”でも、私たちが組み合わせれば全体像が見えます」と、断片的な情報の価値を伝える。 |
| SlackやTeamsで一言、『今日の気づき』のような形で、箇条書き一つでも構いません」と、コミュニケーションのハードルを極限まで下げる。 |
| (できれば)音声入力を推奨する。いちいちタイピングして送ってもらうよりも、整っていなくてもよいので音声で送ってもらう。 |
静的な現状把握(文書・データ・ツールから“客観的な事実”を読み解く)

組織に存在する「静的な情報」から、客観的な事実を読み解いていきます。
資料共有
組織に存在する公式・非公式な文書を体系的に読み解き、プロジェクトの背景、過去の経緯、公式なルール、そして文書化された課題を把握します。
| 対象資料の例 |
|---|
| 経営・戦略関連: 中期経営計画、年度事業計画、取締役会議事録 |
| 業務・運用関連: 各種業務マニュアル、運用手順書、業務フロー図 |
| IT・システム関連: システム構成図、IT資産管理台帳、過去のシステム障害報告書 |
| 人事・組織関連: 組織図、職務分掌規程、人事評価制度の資料 |
| 顧客・市場関連: 顧客からの問い合わせ管理ログ、クレーム報告書、市場調査レポート |
ツール利用状況の把握
現在、組織内でどのようなITツールが、何の業務に、どのように使われているかを正確に棚卸しし、AI導入の技術的な土台と制約を理解します。
具体的な調査項目
| 導入済み/利用中ツール |
|---|
| 各部門、各担当者が日常的に利用しているすべてのソフトウェア、SaaSをリスト化する。 公式に導入されたものだけでなく、現場が独自に利用しているツール(シャドーIT)も、可能であればヒアリングを通じて把握する。 |
| 誰がどの権限のロールで使っているのかも確認する。 例えば、ChatGPTでも有料プランの従業員と無料プランの従業員で別々なことがある。 |
| 専門的な技術スタック |
|---|
| 情報システム部門やIT部門に確認する。社内で利用しているシステム開発文脈での技術スタックを確認する。上記の「導入済み/利用中ツール」は、どの社員でもわかるようなツール名をリストアップするのに対して、こちらの場合は使っているサーバーやプログラミング言語、利用APIなどの専門的な技術スタックを確認する。 |
| ホワイトリスト |
|---|
| 社内で利用が許可されているソフトウェアやクラウドサービスのリストを確認する。 |
| ブラックリスト |
|---|
| 社内で利用が禁止されているソフトウェアやクラウドサービスのリストを確認する。 |
組織構造・規定の確認
組織図や社内規定といった「公式なルール」を把握し、動的な把握で見えた「インフォーマルな力学」とのギャップを分析します。このギャップこそが、AI導入(業務改革)の際の抵抗や障害になりうるのです。
| 確認対象 |
|---|
| 組織図: 公式なレポートライン(指揮命令系統)を理解する。 |
| 職務分掌規程: 各部門、各役職の責任と権限がどこにあるかを把握する。 |
| 人事評価制度: AI導入による業務効率化が、従業員の評価にどう影響するか(あるいは、しないか)を理解する。効率化が評価に繋がらない制度の場合、現場の協力が得られにくい可能性がある。 |
AI導入プロジェクトは、どのようなAIを、どう使うかという『技術選定』が主役だと思われがちです。しかし、数多くのプロジェクトが失敗する本当の理由は、そのずっと手前の段階にあります。
それは、「今、あなたの会社で、どのような業務が、どのように行われているのか」、そして「どこにAI導入の真のチャンスが眠っているのか」を、誰よりも深く、正確に見極めること。
これこそが、プロジェクトの成否の9割を決めると、私たちは確信しています。
コーレ最大の強みは、これまで様々な業界、業種、職種のクライアントワークを通じて培ってきた、圧倒的にスピーディで、正確な『業務理解の解像度』です。
コーレにAI導入プロジェクトをお任せいただければ、ご説明したような「精密な現状把握」からスタートします。そして、机上の空論ではない着実なAI導入プロジェクトをご一緒できることをお約束します。