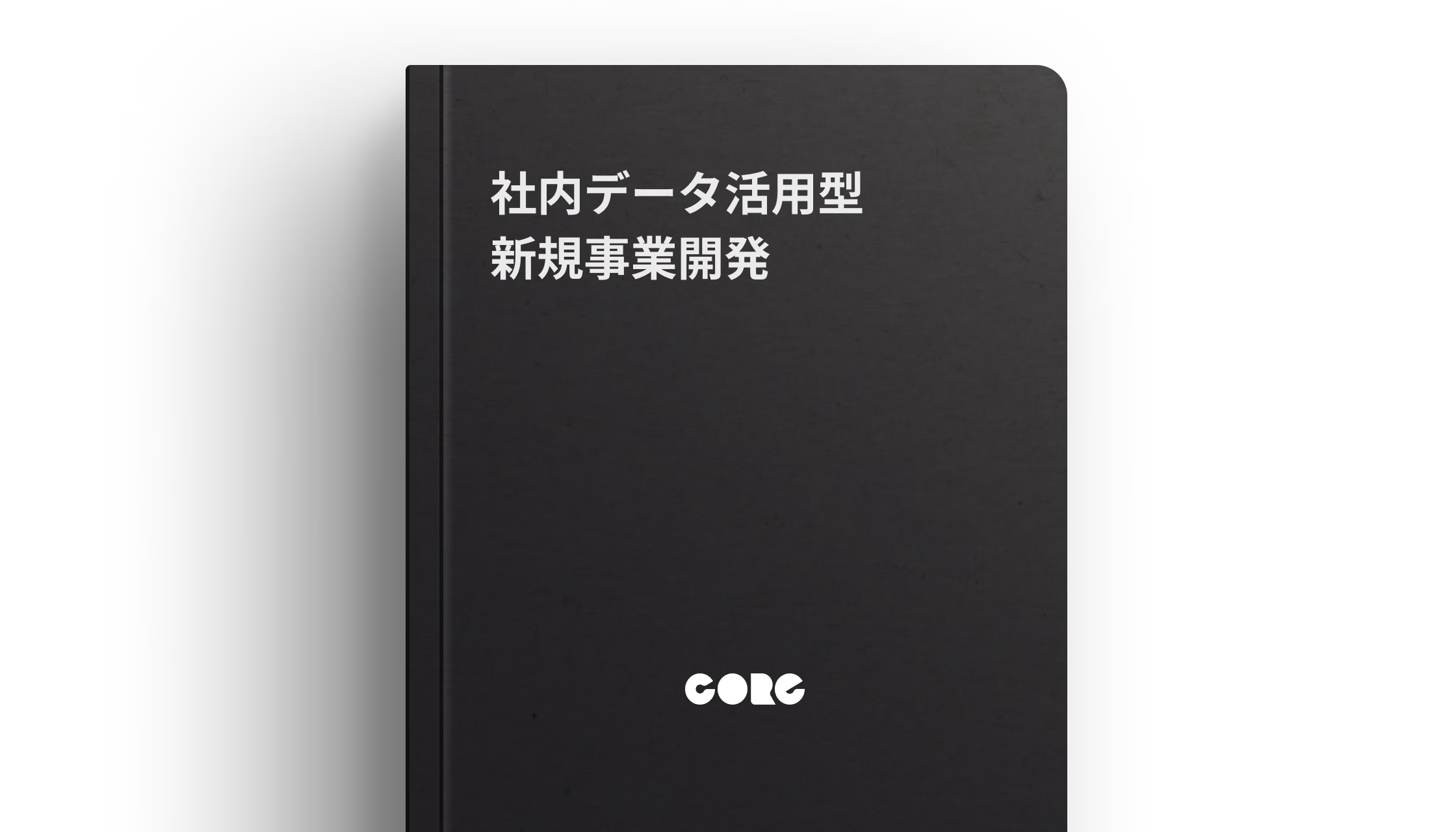「うちの会社には価値のあるデータなんてない」
多くの経営者や事業責任者から聞かれる言葉です。しかし、20年以上にわたり新規事業開発の現場に携わってきた経験から断言できることがあります。それは、データに価値がないのではなく、データの価値を見出す解像度が組織に欠けているということです。
特にAI時代において、この認識の差は企業の生死を分ける要因となりつつあります。生成AIの登場により、データの活用方法は飛躍的に広がりました。しかし、多くの企業はまだその可能性に気づいていません。本稿では、社内データを活用した新規事業開発の本質と、それを実現するための「データ価値共創メソッド」について解説します。
今こそ、社内データ

データ活用の現実と理想のギャップ
現代のビジネスにおいて、「データドリブン」という言葉は既に陳腐化しているかもしれません。しかし、実際にデータを戦略的に活用できている企業はどれほどあるでしょうか。多くの企業では、データは以下のような状態に置かれています。
- 各部門にサイロ化(システムやデータなどが部門ごとに分断されて連携が取れていない状態)され、横断的な活用ができない
- 集計レポートは作成するが、そこから新たな価値を生み出せない
- データの量は増えるが、質的な理解が深まらない
この状況を打破するには、データと向き合う「正当な理由」が必要です。そして、その最も効果的な理由こそが「新規事業開発」なのです。
新規事業開発という触媒
新規事業開発プロジェクトには、組織を動かす強い力があります。それは、部門の壁を越え、普段は触れることのないデータに焦点を当て、複数の視点から価値を探す機会を創出します。
重要なのは、新規事業がうまくいかなくても成功といえることがあるということです。むしろ、新規事業開発のプロセスで得られる「データに対する組織的な理解の深化」こそが、長期的な競争優位の源泉となることが多くあります。
データ解像度を高める3つのステップ

ステップ1:ファクトの発掘と顧客解像度の向上
社内データを活用した新規事業開発において、最初に取り組むべきは「解像度を高める」ことです。これは単にデータを分析することではありません。
ファクトの発掘とは、一般的な認識とデータが示す現実のギャップを見出すことです。例えば、「若者は〇〇を好む」という通説が、実際のデータでは全く異なる傾向を示すケースは珍しくありません。このギャップこそが、新たなチャンスとなります。
また、顧客解像度の向上も必要です。データから見えてくる顧客像は、設計時点のペルソナとは異なる、生々しい現実を映し出します。購買履歴、行動ログ、問い合わせ内容など、断片的なデータを統合することで、顧客のリアルな解像度が浮かび上がってきます。
ステップ2:コンテキストの理解
データは数字の羅列ではありません。その裏側には、人間の感情、社会の動き、時代の変化が潜んでいます。
例えば、ある商品の売上が特定の曜日に急増するというデータがあったとします。単純に「〇曜日は売れる」という理解では不十分です。なぜその曜日なのか、顧客のライフスタイルとどう関係しているのか、競合の動きはどうか。こうしたコンテキストの分析により、データは初めて「使える知識」へと昇華されます。
コーレが携わったプロジェクトでは、BtoBサービスの利用ログから、顧客企業の組織文化や意思決定プロセスまで読み解くことができました。これは、営業部門が何年もかけて蓄積してきた暗黙知を、データから再構築できたということです。
ステップ3:価値創出パターンの選択
データの解像度が高まったら、次は価値創出の方法を選択します。ここで重要なのは、直接的価値創出と間接的価値創出の2つのアプローチを理解することです。
直接的価値創出モデル
これは、データそのものを商品として販売するアプローチです。最近では以下のような形態が増えています。
- データベースのAPI化:蓄積したデータを外部に公開し、利用料を徴収
- インサイトレポートの販売:データから得られた知見をレポート化して販売
- データマーケットプレイスへの出品:業界特化型のデータを専門市場で取引
例えば、不動産会社が長年蓄積してきた地域の賃貸相場データを、API経由で他社に提供するケースがあります。これまで社内でしか使われていなかったデータが、直接的な収益源に変わった例です。
間接的価値創出モデル
間接的価値創出は、データを活用してサービスの価値を高めるアプローチです。
- マッチングサービス:人材紹介のように、データベースを活用して最適な組み合わせを提案
- 予測・最適化サービス:過去のデータから未来を予測し、意思決定を支援
- パーソナライゼーション:個々の顧客に最適化された体験を提供
人材紹介会社は、この間接的価値創出の典型例です。求職者と企業のデータベースという「資産」を持ちながら、データそのものを売るのではなく、マッチングという「価値」を提供して収益を得ています。
最近では、人材データベースを直接的価値創出モデルとして成り立たせるケースも増えてきました。
AI時代における価値増幅
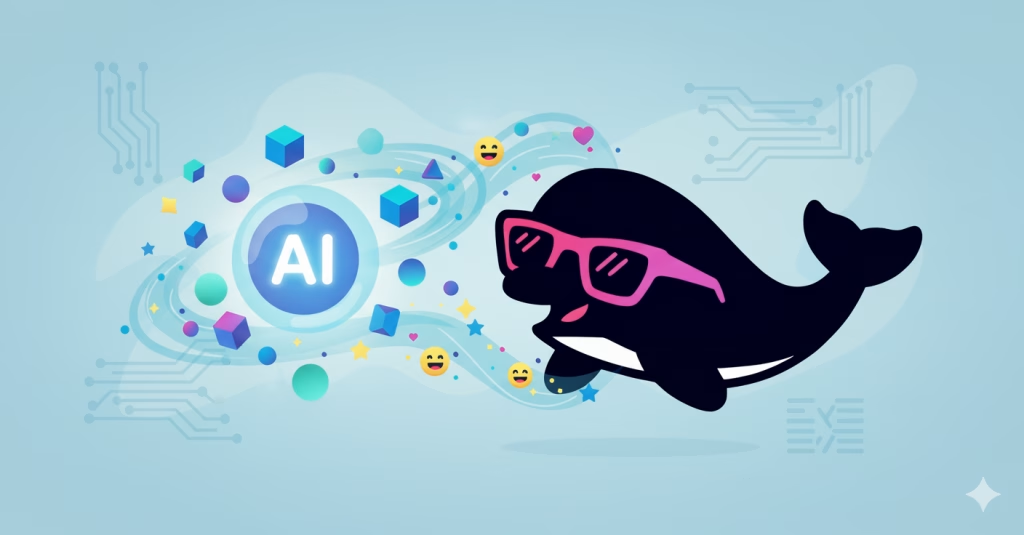
生成AIがもたらす可能性
生成AIによって特に注目すべき可能性は、非構造化データの活用です。議事録、メール、画像、音声など、これまで活用が困難だったデータも、生成AIによって価値ある情報源に変わります。
マイクロAIエージェントという新たなアプローチ
私たちが開発している「AI-BPR CLOUD」では、業務プロセスごとに最適化されたマイクロAIエージェントを配置するアプローチを取っています。これは、巨大な汎用AIではなく、特定の業務に特化した小さなAIを量産する考え方です。
このアプローチの利点は、各企業の固有のデータとプロセスに深く適応できることです。汎用的なAIツールでは見逃してしまう、その企業ならではの価値を最大限に引き出すことができます。
組織的な共通認識の構築
なぜ共通認識が重要なのか
データ活用で最も難しいのは、技術的な課題ではありません。組織全体でデータの価値を共有することです。
営業部門、マーケティング部門、開発部門、経営層。それぞれがデータに対して異なる視点と期待を持っています。新規事業開発プロジェクトは、これらの視点を統合し、共通の理解を生み出す場として機能します。
共通認識がもたらす波及効果
一度、データの価値に対する共通認識が形成されると、その効果は新規事業開発にとどまりません。
- 業務効率化への展開:データの構造と意味を理解したことで、自動化の可能性が見えてくる
- 既存事業の改善:新たな視点から既存サービスの価値を再定義できる
- データ活用文化の醸成:日常的にデータを意識する組織文化が生まれる
競争優位の源泉としてのデータ理解
データ理解力が企業の命運を分ける
AI時代において、技術そのものはコモディティ化していきます。ChatGPTもClaudeも、誰もが使えるツールです。では、何が企業の競争力を決めるのでしょうか。
それは、自社のデータとそのコンテキストを深く理解し、独自の価値を生み出せる組織能力です。この能力は一朝一夕には身につきません。だからこそ、今すぐ始める必要があるのです。
社内データ活用型新規事業開発の3つのステップ

ステップ1:データの棚卸しと価値評価
なぜ最初にデータの棚卸しが必要なのか
社内データ活用型の新規事業開発では、まず「どんなデータがあるのか」を正確に把握することから始める必要があります。なぜなら、社内データは部署ごとにサイロ化していることが多く、経営層でさえ「会社全体でどんなデータを持っているか」を把握していないケースがほとんどだからです。
具体的な棚卸し手順
1. データ保有部署マップの作成
| データ内容 | データ量 | 更新頻度 | 現在の用途 |
|---|---|---|---|
| 顧客訪問履歴 | 月10万件 | ほぼリアルタイム | CRM入力のみ |
| センサーデータ | 日1TB | 1秒ごと | 異常検知のみ |
| 問い合わせ履歴 | 年50万件 | 日次 | FAQ作成 |
2. データの”鮮度”と”独自性”評価
| 点数 | 鮮度スコア | 独自性スコア |
|---|---|---|
| 5点 | リアルタイムで更新される | 業界で当社だけが持つデータ |
| 4点 | 日次で更新される | 競合数社しか持たないデータ |
| 3点 | 週次で更新される | 業界上位企業なら持っているデータ |
| 2点 | 月次で更新される | 多くの企業が持っているデータ |
| 1点 | 年次以下の更新頻度 | 公開情報から取得可能なデータ |
3. クロスデータ可能性の検証
ここが最も重要です。単一のデータセットだけでは新規事業の差別化要因になりにくいため、複数データの掛け合わせ可能性を探ります。
営業部の「顧客訪問履歴」×製造部の「製品稼働データ」
→顧客の設備稼働状況に応じた保守予測サービス
CS部の「問い合わせ履歴」×営業部の「購買履歴」
→購買パターンに基づく問い合わせ予測&セールスサポートAIの開発
ステップ2:市場トレンドとのマッチング
データ×市場トレンドの掛け算思考
社内データがいくら独自性があっても、市場ニーズがなければビジネスにはなりません。そこで重要なのが「蓄積された情報×市場でキテいるものの掛け合わせ」という発想です。
トレンドキャッチの具体的手法
3つの情報源からトレンドを収集
- 海外スタートアップ動向
- Crunchbase、CB Insightsなどで資金調達情報をチェック
- 特に「Data-driven」「AI-powered」というキーワードで検索
- 月間10億円以上の調達をしている企業をリストアップ
- 大手企業の新規事業発表
- 競合だけでなく異業種の動向も含めてウォッチ
- 特に「データ活用」「DX」関連のプレスリリース
- 四半期決算説明会での新規事業言及をチェック
- 規制・政策動向
- データ利活用に関する規制緩和の動き
- 政府のDX推進施策(補助金情報含む)
- 業界団体のガイドライン改定
トレンドと社内データのマッピング
収集したトレンドを、先ほどの社内データと掛け合わせます。[社内データ] × [市場トレンド] = [新規事業アイデア] です。
例1:
製造ラインセンサーデータ × カーボンニュートラル需要
= CO2排出量可視化・削減コンサルティング事業
例2:
顧客購買履歴データ × サブスクリプション化の波
= BtoBサブスク最適化支援サービス
例3:
設備稼働データ × 予知保全AI市場の成長
= AI予知保全プラットフォーム事業
3. 市場規模とタイミングの見極め
アイデアが出たら、以下の観点で優先順位をつけます。
Too Early:技術的に未成熟、規制が厳しい
Just Right:競合が少なく、需要が顕在化し始めている
Too Late:すでにユニコーン企業が存在する
ステップ3:PoC設計と初期投資戦略
なぜスモールスタートではダメなのか
一般的なスタートアップなら「まずは小さく始めて検証」が鉄則ですが、社内データ活用型新規事業では話が違います。なぜなら、
- データ整備に初期投資が必要
- データクレンジング
- API開発
- セキュリティ対策
- 競争優位性の源泉がデータ量
- 少量のデータでは差別化できない
- ネットワーク効果を生むには臨界点が必要
- 顧客の期待値が高い
- 大手企業発のサービスには完成度が求められる
- β版では相手にされない
PoC設計の実践的テクニック
2段階PoC方式がおすすめです。
第1段階:社内PoC
自社内の別部署をお客様に見立てて実施
データ連携の技術的課題を洗い出し
UIUXの初期検証
第2段階:限定顧客PoC
信頼関係のある顧客3〜5社に限定
有償PoC(本サービスの30%程度の価格)
失敗を避けるためのチェックリスト
事業開始前のチェック項目
□ 経営トップのコミットメントは取れているか
□ 3年間の予算確保の見通しはあるか
□ データガバナンス体制は整っているか
□ キーとなる人材の確保・育成計画はあるか
□ 既存部門との調整は済んでいるか
開発フェーズのチェック項目
□ プレスリリースを書けているか
□ 最初の顧客と、次の顧客を集める具体的な方法は設計できているか
□ 顧客の声を週次で聞いているか、もしくは聞く体制は作れるか
□ データ品質の定量的な管理はできているか
□ 競合動向をウォッチできているか
事業拡大フェーズのチェック項目
□ スケールする前提体制になっているか
□ カスタマーサクセス体制は整っているか
□ データ分析人材の採用は進んでいるか
□ ゴール像は描けているか
社内データ活用型新規事業開発は、通常の新規事業とは異なり、優位性を持って始めることができます。
重要なのは、「社内データから見えてくるものが何かを徹底的に解像度を高くする」という視点です。そして、小さく始めようとせず、競争優位性を築けるだけの投資を最初から行う覚悟も必要です。
今すぐ始めるべき理由

「うちにはまだ早い」「もう少しデータが溜まってから」
こうした声もよく聞きます。しかし、完璧なタイミングなど存在しません。むしろ、不完全なデータと格闘する過程でこそ、組織は成長します。
重要なのは、データ活用を特別なことではなく、日常的な企業活動の一部にすることです。新規事業開発という挑戦的な目標を掲げることで、組織は限界を超えて成長できます。
AI時代の競争は、既に始まっています。自社のデータという宝の山に気づき、その価値を最大化できる企業だけが、次の10年を生き残ることができるでしょう。
私たちコーレは、AI-BPR CLOUDをはじめとする様々なソリューションで、企業のデータ活用を支援してきました。しかし、最も重要なのはツールではありません。データと向き合う覚悟と、そこから価値を生み出そうとする意志です。
今こそ、データという資産と真剣に向き合う時ではないでしょうか。