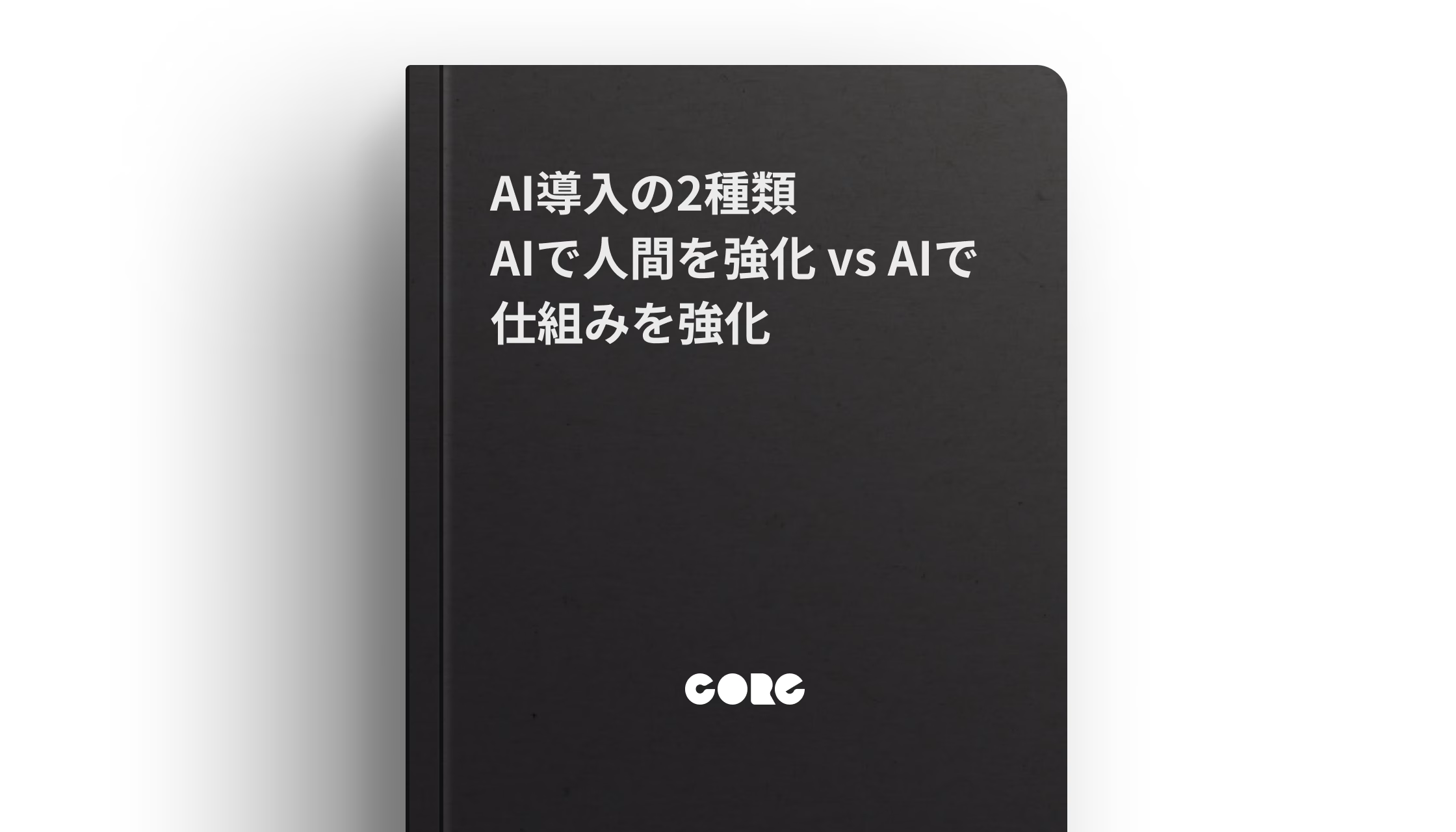会社として「AI導入で生産性を上げたい」と決めたとき、どんなAI活用をイメージするでしょうか。社員一人ひとりがChatGPTやGeminiなどを使いこなす姿でしょうか。それとも、業務フローに組み込まれたAIが自動で処理を進めていく姿でしょうか。
実は、この最初のイメージのズレが、AI導入プロジェクトの成否を分けます。私たちがこれまで多くの企業のAI導入を支援してきて気づいたのは、AI導入には明確に2つの種類があり、それを混同したままプロジェクトが進むと、必ずと言っていいほど事故るということです。
この「AI導入の2種類」について、実践的な視点でお伝えします。
AI導入の2つのアプローチ
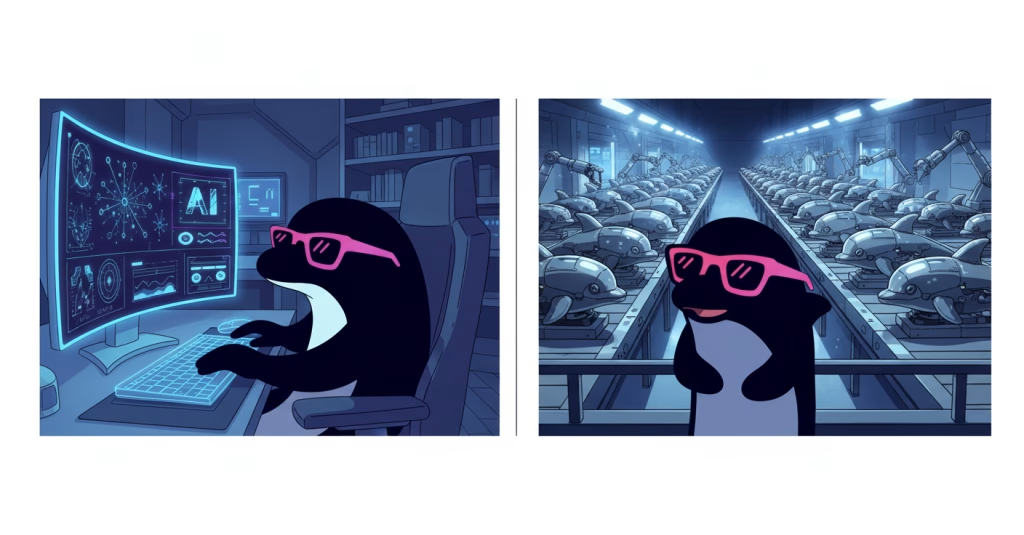
AI導入には、大きく分けて2つのアプローチがあります。
アプローチ1. AIで人間を強化する
これは、社員一人ひとりがAIツールを使いこなすことで、個々のスキルを拡張し、1人あたりの生産性を高めるアプローチです。
例えば、営業担当者がChatGPTで提案資料を作成したり、マーケターがAIで市場分析を行ったり、デザイナーが生成AIでデザインのバリエーションを量産したり。人間が主役で、AIはその能力を増幅させる道具として機能します。
アプローチ2. AIで仕組みを強化する
一方、こちらは業務プロセスそのものにAIを組み込み、社員のAIスキルに関係なく、システムとして全体の生産性を高めるアプローチです。
例えば、問い合わせ対応を自動化するチャットボット、書類の内容を自動で判定・分類するシステム、在庫予測を行う需要予測AIなど。仕組みが主役で、AIはその仕組みの一部として埋め込まれます。
それぞれの特徴を理解する
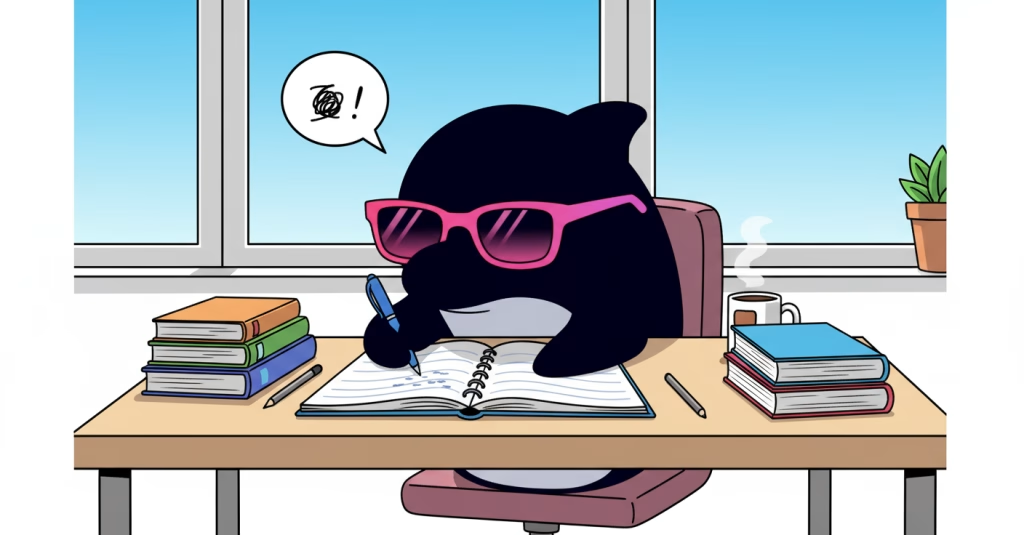
AIで人間を強化する場合
メリット:
- 導入が比較的容易で、既存のAIツールを使えばすぐに始められる
- インパクトが大きい。優秀な社員がAIを使いこなせば、生産性は2倍、3倍にもなる
- 柔軟性が高く、状況に応じて使い方を変えられる
- 小さく始めて、段階的に広げていける
デメリット:
- 人間がボトルネックになる。習熟度に個人差が大きく、使いこなせる人とそうでない人の差が激しい
- 属人化リスクがある。AIを使いこなせる優秀な社員が離職すると、一気に生産性が下がる
- 継続的な教育が必要。新しいツールが出るたびに学び直す必要がある
- 体調不良や休暇など、人間ならではの不確実性がある
多くの場合、このアプローチを徹底できるとインパクトが大きいです。なぜなら、社員の業務ドメイン知識とAIの処理能力を組み合わせることができるので、AIに与えるデータを整えるなどの前処理工数が低く、導入コストを抑えながら、柔軟に確実にパフォーマンスを上げていけるからです。
しかし、徹底することが難しく、人間のもともとのITリテラシーなどによって大きく差が出ます。さらに社内に抵抗勢力が発生してうまく進まないこともあります。
AIで仕組みを強化する場合
メリット:
- 品質が安定する。人によるバラツキがなく、24時間365日同じクオリティで稼働
- スケールしやすい。一度構築すれば、人数を増やさずに処理量を増やせる
- 属人化を防げる。特定の人に依存しない
- 長期的には効率的。初期投資は大きいが、運用コストは低い
デメリット:
- 導入に多大なコストと時間がかかる。システム開発、データ整備、テスト、運用設計など
- 柔軟性に欠ける。一度構築すると、変更するのに大きなコストがかかる
- 初期投資のハードルが高い。経営層の強いコミットメントが必要
- 失敗したときのダメージが大きい
このアプローチは、業務が標準化されていて、変化が少ない領域で特に有効です。社員の数が1000人を超えてくるような場合などは非常に大きなインパクトがあります。
しかし、そもそも業務が標準化されているケース自体が少なく、多くの場合はAI導入=業務改善コンサルティングがセットになることが多いです。導入までの時間がかかります。
どちらが良いというわけではない

ここまで読んで、「じゃあ、どちらを選べばいいの?」と思われるかもしれません。答えは、「それは状況による」です。
例えば、判断が必要な業務や、各々が頑張って行う努力値によって品質や速度が変わる業務は「人間を強化」するアプローチが向いています。一方、定型的で繰り返しの多い業務は「仕組みを強化」するアプローチが向いています。
また、組織の成熟度や予算、スピード感によっても最適な選択は変わります。スタートアップなら柔軟性が高い「人間を強化」から始めるべきでしょうし、大企業で安定的な業務改善を目指すなら「仕組みを強化」が適しているかもしれません。
どちらが優れているかではなく、目的と状況に応じて使い分けることが重要なのです。
本当に怖いのは「認識のズレ」

そして、ここからが最も重要な話です。
どちらのアプローチを選ぶかよりも、どちらのAI導入の種類なのかを誤った認識のままプロジェクトが進むことが、最悪の事態なのです。
私たちがこれまで見てきた失敗プロジェクトの多くは、このズレが原因でした。経営層は「仕組みを強化」するつもりで予算を承認したのに、現場は「人間を強化」するツール導入だと思っていた。あるいは、その逆。このズレに気づかないまま数ヶ月が経過し、お互いに「話が違う」となって頓挫する。
これを例えるなら
この状況を例えるなら、「カーナビを買いに行ったつもりが、自動運転車を開発するプロジェクトになっていた」ようなものです。
カーナビ(AIで人間を強化)は、ドライバーである人間が最終的な判断をしながら、より効率的に目的地にたどり着くための道具です。数万円で買えて、すぐに使い始められ、運転者の腕次第で活用度も変わります。
一方、自動運転(AIで仕組みを強化)は、システムそのものが運転を行います。開発に数億円かかり、完成まで数年を要し、一度作れば誰が乗っても同じように目的地に着けます。でも、途中で「やっぱり違う技術で」と変更するのは非常に困難です。
どちらも「車での移動を便利にする」という目的は同じですが、必要な予算、期間、体制、リスク、リターン、すべてが桁違いに異なります。
カーナビを買う予算で自動運転車の開発を始めようとする人はいません。逆に、自動運転車が必要なのにカーナビを配って「これで生産性が上がる」と言っても、根本的な解決にはなりません。
でも、AI導入の現場では、これと同じことが日常的に起きているのです。
なぜズレが生まれるのか

なぜこのようなズレが生まれるのでしょうか。
理由の一つは、「AI」という言葉があまりにも広い概念を指しているからです。ChatGPTもAI、自動運転もAI、顔認証もAI。すべて「AI」という一言で語られるため、具体的なイメージが人によって全く異なってしまいます。
もう一つの理由は、どちらのアプローチも「生産性向上」という同じ目標を掲げるため、表面上は同じプロジェクトに見えてしまうことです。
そして最も厄介なのは、プロジェクトの初期段階では、このズレに気づきにくいということです。「AI導入で業務を効率化しましょう」というざっくりとした合意でプロジェクトがスタートし、具体的な要件定義に入ってから「あれ、話が違う」となるのです。社内のAIの知識や経験が不足していることにより、違和感を感じる頃にはすでに手遅れになっていることが多くあります。
プロジェクト開始前に確認すべきこと
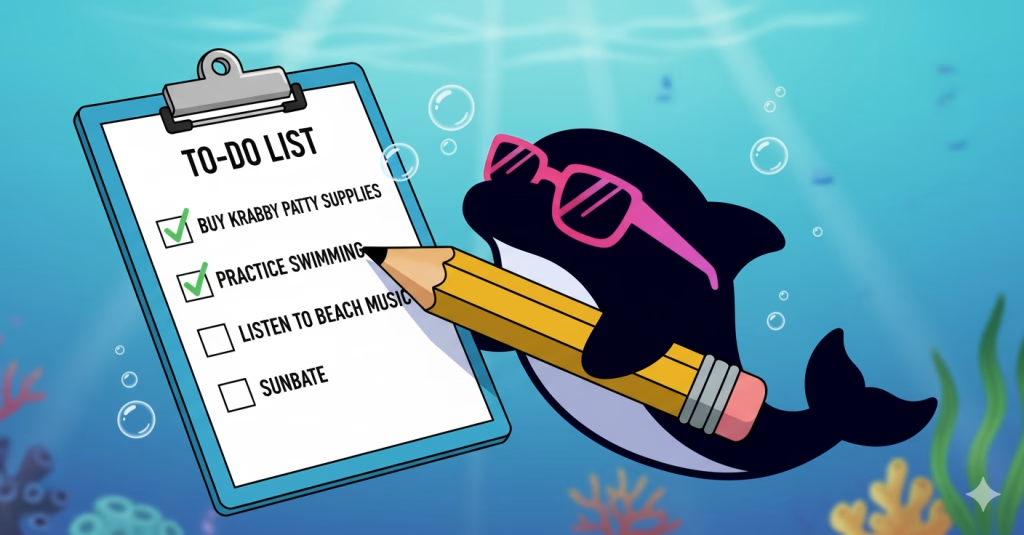
では、このズレを防ぐためには、どうすればいいのでしょうか。プロジェクトを始める前に、関係者全員で以下の点を明確にすることをお勧めします。
1. このAI導入は、誰が主役なのか?
- 人間が主役で、AIは道具なのか
- AIが主役で、人間は補助なのか
2. 成功の定義は何か?
- 「優秀な社員の生産性が3倍になること」なのか
- 「誰が担当しても同じ品質で処理できること」なのか
3. 投資の規模感はどのくらいか?
- 数十万円〜数百万円なのか
- 数千万円〜数億円なのか
4. いつまでに、どの程度の効果を期待するのか?
- 1ヶ月で一部の業務に効果が出れば良いのか
- 1年かけて全社的な仕組みとして完成させるのか
5. 柔軟性と安定性、どちらを優先するのか?
- 状況に応じて変化できることが重要なのか
- 一度決めたら変わらないことが重要なのか
これらの質問に対する答えを、経営層、プロジェクトマネージャー、現場担当者がそれぞれ出してみてください。もし答えがバラバラなら、それはズレが生まれるサインです。プロジェクトを本格的に始める前に、認識を揃える必要があります。だからAIの知識や経験が豊富な人間がプロジェクトには必要なのです。成功も失敗も経験している人間がいないと、このアプローチに対する勘所がないのです。
両方を組み合わせるという選択肢

ちなみに、必ずしもどちらか一方を選ぶ必要はありません。多くの成功企業は、両方のアプローチを戦略的に組み合わせています。
例えば、定型的な業務は「仕組みを強化」して自動化し、細かい業務は「人間を強化」してAIツールで支援する。こうすることで、安定性と柔軟性の両方を手に入れられます。ただし、この場合も「今取り組んでいるのはどちらのアプローチなのか」を常に明確にしておく必要があります。
まとめ:AI導入の成功は、最初の認識合わせで決まる

AI導入には「人間を強化」と「仕組みを強化」の2つのアプローチがあり、どちらも有効ですが、性質は大きく異なります。
最も避けるべきは、どちらのアプローチなのかを誤った認識のままプロジェクトを進めることです。これは、カーナビを買いに行ったつもりが自動運転車の開発プロジェクトになっているようなもので、途中で必ず大きな問題が発生します。
AI導入プロジェクトを始める前に、まず関係者全員で「このプロジェクトは、どちらのアプローチなのか」を明確にしましょう。その認識合わせこそが、AI導入成功への第一歩です。
AI導入を検討されている方は、まず「どちらのアプローチが適しているのか」を整理するところから始めてください。