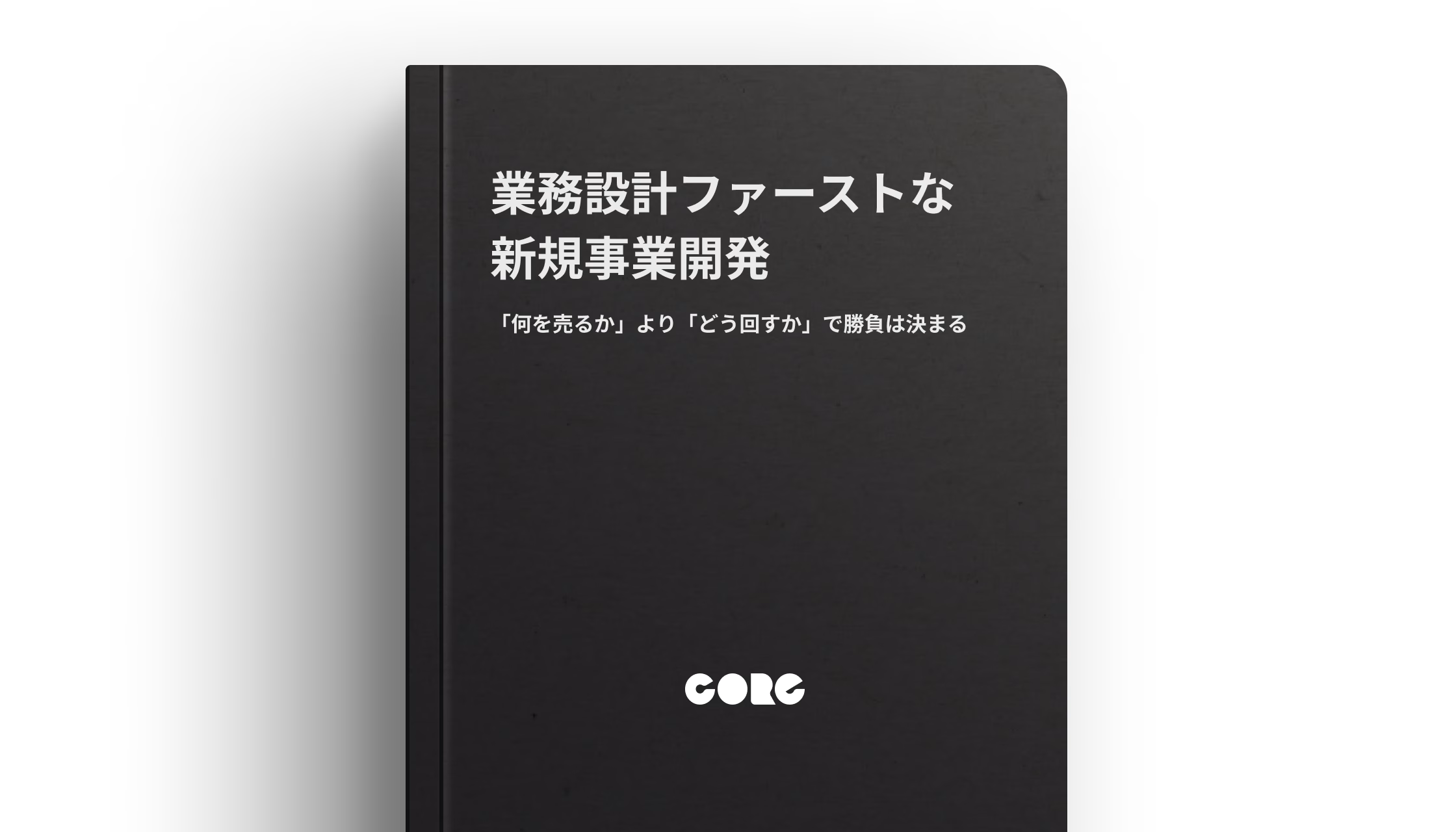新規事業開発で経験者が有利な理由

業務プロセスの解像度が、成功確率を左右する
新規事業開発において、その領域の経験者が圧倒的に有利だと言われるのには、明確な理由があります。
それは、業務プロセスに対する解像度が著しく高いからです。
事業開発において、単なるアイデアや戦略だけでは実際の成果にはつながりません。
重要なのは、それをどのようなプロセスで日々の業務として回すかを具体的に描けるか、つまり「動かせる事業設計」ができるかどうかです。
このとき、業界経験者や類似事業の運営経験者は、
- 「こういう場面では、こういう作業が発生する」
- 「このフェーズでは、こういうトラブルが起きやすい」
- 「この数値をチェックしないと、後で大きなロスにつながる」
といった、言語化しづらい現場の動きや勘所をリアルにイメージできています。
一方、未経験者が机上で立てたプランには、しばしば欠陥が生じます。
抽象的なToDoだけが並んでいて、肝心の運用ステップが抜けている。
実務レベルの負荷やリスクを軽視し、過剰な期待に基づく設計になってしまう。
現場の動きに合わせた調整や修正ができず、運営フェーズで手詰まりになる。
だからこそ、新規事業開発においては、その領域における業務プロセスのリアルな知見が、成功確率を劇的に高める要素となるのです。
事業を成功させたいなら、単なる市場の魅力やアイデアだけで判断してはいけません。
「誰が、どのレベルで業務を設計・運営できるか」という視点を、最初から組み込んでおくべきです。
新規事業の現場で感じる社内コミュニケーションの手間もクリアできる

会社のアセットを使って新規事業をやるとしても、新しい試みをする以上、どう業務をまわすのかをある程度あらかじめ描けていないといけません。
とはいえ、正直なところ、具体的な業務プロセスなんて、実際にやってみないと高い解像度ではわからないものです。
バックオフィスや経営層からは「業務フローを教えて」と言われますが、「そんなの、やりながら固めるんだよ。机の上で業務フローをコネコネしている時間があるなら、見込み顧客のN1を見つけることに時間を使いたいんだよ」というのが、現場としての本音ではないでしょうか。
でも、会社のお金とリソースを使う以上、きちんと説明する動きも求められます。
つまり、事業を伸ばすための行動と、社内に向けた説明責任の両立をしなければならないわけです。
だからこそ、業務プロセスの設計が必要になります。
具体的に、どのように業務を動かしていくかを、ある程度描き出す必要があります。
また、予算を組むときには、どんなツールが必要で、どれくらいの工数がかかるかも算出しなければいけません。
先に新規事業に必要な業務プロセスとツールとシステムとリソースを、超具体的に算出できると、説明コストも事業づくりのスムーズさも、桁違いに楽になります。
なぜ「業務プロセス先行」が有効なのか?

① 立ち上げ初期の「手戻りコスト」が激減する
新規事業の立ち上げで怖いのと同時に必ずぶち当たるのが、「あれ、思っていたのと違う」現象です。
営業活動を始めたら請求書の発行方法が決まっておらず、バタバタ対応する。
初回納品のタイミングで契約書周りの不備が発覚し、信用を落とす。
こうした”手戻り”が続くと、現場はすり減り、顧客にも不信感を与えます。
業務プロセスを先に描いておけば、こうした「予期せぬ詰まり」を事前に塞ぐことができます。
業務設計とは、事業の配管工事のようなものです。
水(商流)がスムーズに流れるように、最初にきちんと設計しないと、後で漏水(トラブル)が起きます。
② 社内説明と稟議が一撃で通る
新規事業において最も疲れるのが、「社内向け説明」のループです。
会社のリソースを使う以上、社内から「この投資は本当に正しいのか?」と何度も問いかけられます。
このとき、「どんな業務を、どんな流れで、どれくらいのコストで、どんなリスクを管理して、どう拡張するか」まで説明できると、話が一気に進みます。
稟議書もスムーズに通り、関係部署の協力も得やすくなるのです。
説明責任を果たすためにも、業務プロセスを描き切る力が求められます。
業務プロセス設計の具体的ステップ

新規事業における業務プロセス設計は、きれいなフローをいきなり作るものではありません。
重要なのは、非構造的にカオスを出し切ることから始めることです。
ここから順を追って、実践的な手順をお伝えします。
ステップ1:粗くてよいので、業務の開始から終わりまでをひたすら書き出す(具体設計)
まず最初にやるべきことは、頭の中にある業務イメージを非構造的に全て書き出すことです。
順番も正確さも、ここでは一切気にしません。
- 営業リストを作る
- メールを送る
- 初回面談をセットする
- 契約書を取り交わす
- 請求書を発行する
- サービスを納品する
- 顧客フォローをする
といった具合に、思いつく限り、業務のスタートからゴールまで、ひたすら具体的に書き出していきます。
この段階では、「え、これって業務に含まれるのかな?」と思うものも遠慮せずに書いてください。
最初はカオスでいいのです。
なぜなら、カオスがなければ整理もできないからです。
ステップ2:構造的に整理する
非構造的に書き出した業務群を、ここで構造化していきます。
つまり、似た業務同士をグルーピングしたり、業務同士の前後関係を明らかにする段階です。
- リード獲得
- 顧客への初回接触
- 商談設定
- 契約締結
- サービス提供
- 顧客サポート
- 請求と回収
というふうに、大きな流れにまとめ、各フェーズごとの業務タスクを整理していきます。
ここではじめて、「業務の流れ」というものが立ち上がってきます。
ステップ3:フローチャートなどで可視化する(抽象化)
次に、整理した業務群を図で可視化します。
ここでは「フローチャート」や「業務プロセスマップ」などを使うのがおすすめです。
文字情報だけだと、人によって頭の中のイメージがバラバラになります。
図にすることで、全体像が一目で把握でき、関係者間の認識齟齬を防ぐことができます。
この段階で意識すべきなのは、細かいタスク同士の関連性を、できるだけシンプルに描くことです。
フローが複雑になりすぎる場合は、まず大枠だけを描き、詳細は別紙に分けてもかまいません。
ステップ4:人間の作業、システムの作業、他者とのコミュニケーション作業を分類する(仕分け)
最後に、可視化した業務の中で、誰が何をやるのかを仕分けます。
- 人間が手動で行う作業
- システムが自動で処理できる作業
- 顧客や外部パートナーとのコミュニケーションが発生する作業
この3種類に色分けしたり、アイコンを付けたりして分類します。
- 自動化すべき箇所
- 人のスキルが必要な箇所
- 外部との調整が必要な箇所
が一目でわかるようになり、業務改善やツール導入の議論がスムーズになります。
業務プロセス設計は、事業開発の「見えないインフラ」

新規事業開発において、業務プロセス設計は一見地味な作業に思えるかもしれません。
目に見えるプロダクトやサービス設計に比べれば、注目もされにくい。
しかし、業務プロセスこそが、事業を支える見えないインフラです。
インフラが脆弱なら、どれだけ魅力的な商品をつくっても、事業は長続きしません。
そして、業務プロセスを設計できるということは、「この事業を、どうやって社会に実装するか」の道筋を描けるということです。
新規事業開発とは、アイデアを社会に橋渡しする営みです。
その橋をかける作業が、業務プロセス設計なのです。
机上の空論ではなく、実態ある設計を。
思考停止のコピーではなく、自分たちの現場に即した業務を。
それができるチームは、どんな新規事業にも強くなれます。
業務設計を阻む落とし穴
一方で、業務設計にはまちがったアプローチも存在します。
ここでは、ありがちな失敗パターンについても触れておきます。
① 最初から完璧を求めてしまう
業務設計でよくある失敗は、「最初から100%正しい業務フローを作ろう」としてしまうことです。
しかし、事業は生き物です。
特に新規事業では、顧客の反応、市場環境、競合の動きによって、どんどん状況が変わります。
最初から完璧な業務を描こうとすると、机上で理想論ばかりをこね回し、実態と乖離してしまう危険性が高い。
業務設計のコツは、「仮説で描き、検証しながら柔軟に更新していく」ことにあります。
② 業務設計が現場目線になっていない
もう一つのよくある罠は、「管理部門の都合」で業務設計を組んでしまうことです。
現場の営業やカスタマーサクセスの実態を無視し、管理コスト最小化を優先してしまう。
すると、現場がやりづらくなり、パフォーマンスが落ちます。
業務設計の本質は、事業を伸ばすための業務を設計することです。
新規事業成功のカギは「業務プロセスの先行設計」にある
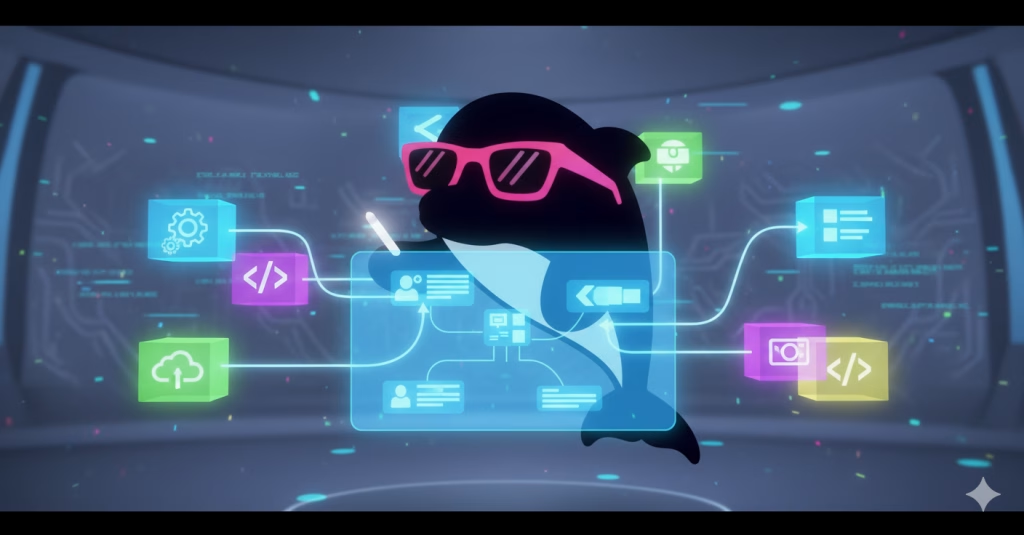
ここまでお伝えしてきた通り、新規事業において、業務プロセス設計は「面倒だけど絶対に手を抜けない領域」です。
業務プロセス設計を先にきちんと描き、ツール・システム・リソースを具体的に定義しておけば、
- 手戻りリスクを激減できる
- 社内説明コストを削減できる
- 現場の実行力を最大化できる
- スケール時の拡張性を確保できる
という、圧倒的なアドバンテージを手にすることができます。
もちろん、業務設計は一発で完成するものではありません。
仮説ベースで描き、現場運用で検証し、改善を繰り返す。
そのプロセス自体が、事業を成熟させるための「成長装置」になります。
新規事業の成長装置を生み出すAI-BPR CLOUD
コーレが独自開発しているAI-BPR CLOUDは、まったく新しい業務プロセスでも、最小単位の業務の仕分けから、あらゆる業務プロセスを整理して可視化します。
また、AIを活用することを前提として業務プロセスを設計できるため、少人数で高い生産性を生み出すために必要なAIの設計も込みで実現できる、AI時代の新規事業開発に打って付けのクラウドプロダクトです。

コーレができること
コーレでは、AI-BPR CLOUDを活用してあらゆる業界業種職種の業務プロセスを即座に整理して新規事業開発の伴走コンサルティングをしています。
お問い合わせお待ちしています
コーレは、戦略コンサルタント、デザイナー、エンジニアが中心となり、AIとビジネスをつなぐAIコネクティブカンパニーです。戦略・企画から制作や開発、マーケティング支援や営業代行まで、一気通貫で上流から末端まで担うパートナーとして伴走します。お客様の要望に沿ったオーダーメイドなサポートをします。
お気軽にご連絡ください:https://co-r-e.net/contact/
コーレについてもっと知りたい方は、こちらから会社パンフレットをご覧ください:コーレ株式会社パンフレット